1. はじめに

「医療麻薬」と聞くと、多くの人が「危険な薬」「依存性が強い」というイメージを持つかもしれません。
確かに麻薬は、適切でない使用や乱用によって健康被害をもたらす可能性があります。しかし、医療の現場では痛みに苦しむ患者のQOL(生活の質)を守るために、必要不可欠な薬です。
日本では「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき、医療麻薬の使用は厳しく管理されています。処方・調剤・保管・使用記録など、あらゆる段階で安全性確保のためのルールが定められています。薬剤師はその制度の中で、医療麻薬が適正に使われるよう監視・管理し、患者や家族の不安を和らげる役割を担います。
2. 医療麻薬の種類と用途

医療麻薬は主にオピオイド系鎮痛薬を指します。代表的な薬には以下があります。
- モルヒネ:経口剤、注射剤、坐薬など多様な製剤があり、がん性疼痛治療の第一選択薬。
- オキシコドン:モルヒネに比べ消化器症状がやや少ないとされる。経口徐放錠や即放錠がある。
- フェンタニル:強力な鎮痛作用を持ち、貼付剤や注射剤として使用。在宅医療でも貼付剤は広く用いられる。
- ヒドロモルフォン:比較的新しい薬で、即効性・持続性を併せ持つ。
投与経路
経口投与(錠剤・カプセル・液剤)、経皮投与(貼付剤)、静脈注射、皮下注射、坐薬など、患者の状態に応じて選択します。たとえば嚥下が困難な終末期患者には貼付剤や坐薬が有効です。
用途
医療麻薬は以下の場面で使われます。
- がん性疼痛の緩和
- 慢性疼痛(神経障害性疼痛など)の一部
- 手術後や外傷後の急性期の強い痛み
- 緩和ケア領域での呼吸困難の緩和
がんや進行性疾患に伴う難治性の呼吸困難に対して、少量のモルヒネを中心とするオピオイドが症状緩和目的で用いられます。国内のガイドラインも、適切な用量設定と観察のもとでの使用を推奨しています(鎮痛目的とは区別し、呼吸抑制に注意)。
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)などの非麻薬性鎮痛薬と異なり、オピオイドは痛みの伝達経路そのものを抑えるため、非常に強力な鎮痛効果を発揮します。
3. 作用機序と薬理学的特徴
医療麻薬の多くは、脳や脊髄に存在するオピオイド受容体(μ受容体、κ受容体など)に結合します。これにより、痛みの信号が中枢神経に届くのを抑え、痛みの感じ方そのものを軽減します。
耐性と依存性
長期使用では、同じ量では効果が得られにくくなる「耐性」が生じる場合があります。また、身体が薬に適応してしまい、急に中止すると離脱症状(発汗、焦燥感、不眠など)が出る「身体的依存」も起こり得ます。ただし、医師の管理下で適切に投与・減量すれば、これらは安全にコントロール可能です。
4. 安全な使用と管理体制

処方(麻薬処方箋)
麻薬は麻薬施用者免許を有する医師等による麻薬処方箋で処方されます。処方箋には、患者情報、品名・分量・用法用量、麻薬施用者の署名(押印)と免許番号、発行日、使用期間などの記載事項が必要です。薬局は疑義照会を適切に行い、麻薬処方箋を3年間保存します。
保管
薬局・医療機関では麻薬を施錠可能な専用保管庫(麻薬金庫)に保管し、期限切れや調剤済みを含めすべて金庫内管理とします。
記録
薬局は麻薬帳簿を備え、受払を都度記録します(法第38条)。不備・不審な処方箋は調剤不可で、医師等に疑義照会が必要です。
返納・廃棄
患者の死亡等で家族から返却された調剤済み麻薬は、薬局開設者または管理薬剤師が立会者の下で廃棄し、30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を都道府県知事へ提出、帳簿(または補助簿)に記録します。病院・診療所でも外来患者からの返納に関する補助簿の整備・記載方法が示されています。
(参考)フェンタニル貼付剤の適正使用
フェンタニル貼付剤はがん疼痛に加え、条件下で非がん性慢性疼痛にも適応があります(他オピオイドからの切替等)。調剤時に確認書の取り扱い等、リスク最小化手順が示されています。
5. 副作用とその対策
医療麻薬は強力な効果を持つ一方で、副作用もあります。
- 便秘:腸管の動きが抑えられるため、ほぼ必発。予防的に下剤を併用することが推奨されます。
- 吐き気・嘔吐:投与開始時に多い。制吐薬の併用で軽減可能。
- 眠気・めまい:慣れとともに軽減することが多いが、高齢者では転倒に注意。
- 呼吸抑制:過量投与や急速投与で起こる危険な副作用。特にオピオイド初回使用時や増量時は慎重に。
薬剤師は副作用を予測し、あらかじめ対策を講じることが重要です。
6. 患者・家族への説明ポイント

医療麻薬に対して「中毒になるのでは?」という不安を持つ患者や家族は少なくありません。説明時には次のような点を強調します。
- 医療麻薬は痛みを取るために使い、快楽目的ではないこと
- 適正量で使用すれば依存のリスクは低いこと
- 副作用や離脱症状は医療者が管理し、必要に応じて減量や中止が可能であること
- 痛みを放置することの方が、生活の質や回復に悪影響を及ぼすこと
こうした説明は、服薬アドヒアランス(治療への協力度)を高めるためにも欠かせません。
7. 最新動向と薬剤師の関わり
近年では、患者の負担を減らす新しい製剤も登場しています。
例として、長時間作用型の徐放性製剤や、貼付剤の改良版があります。これにより服薬回数が減り、在宅療養中の患者にも使いやすくなっています。
WHOが提唱する疼痛治療ラダーでは、痛みの強さに応じて薬を段階的に使い分けることが推奨されています。薬剤師は、この考え方を踏まえて処方内容の妥当性を確認し、必要に応じて医師に提案できます。
また、在宅医療では、薬剤師が直接患者宅を訪問して薬の効果や副作用をチェックするケースも増えています。麻薬帳簿の管理や在庫確認も薬剤師の重要な業務です。
8. まとめ

医療麻薬は「危険な薬」ではなく、「痛みに苦しむ患者を支える薬」です。
厳格な法律と管理体制のもと、適正に使うことで、患者の生活の質を大きく改善できます。薬剤師はその適正使用を支える立場として、薬の管理、患者・家族への説明、副作用対策まで、多方面で重要な役割を果たしています。
痛みを抱える患者にとって、医療麻薬は希望をもたらす存在です。正しい知識と理解を持ち、安心して使える環境を作ることが、私たち医療従事者の使命です。
参考資料
- 厚生労働省.使用ガイダンス(がん疼痛)https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245820.pdf
- 厚生労働省. 麻薬及び向精神薬取締法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81102000&dataType=0&pageNo=1
- 日本緩和医療学会.呼吸困難の薬物療法ガイドライン 2023年版https://www.jspm.ne.jp/files/guideline/respira_2023/respira2023.pdf
- 厚生労働省.麻薬管理マニュアル(薬局向け)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/mayaku_kanri_02.pdf
- 厚生労働省.医療用麻薬適正使用ガイダンスhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/iryo_tekisei_guide2017b.pdf

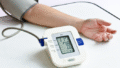

コメント