はじめに
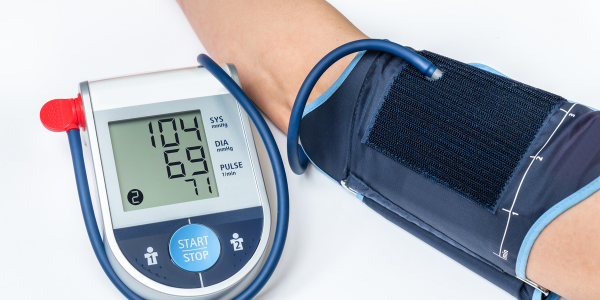
高血圧治療において、カルシウム拮抗薬(Calcium Channel Blocker:CCB)は非常によく使われる薬です。病院や薬局で処方される降圧薬の中でも、長年の実績と安全性の高さから第一選択薬として用いられることも多く、日本では特に高齢者に広く処方されています。
しかし、一口に「カルシウム拮抗薬」と言っても、薬の種類や分類によって得意・不得意があり、降圧効果の特徴、副作用、相互作用も異なります。適切な薬を選ばないと、効果が不十分になったり、副作用が強く出たりする可能性があります。
この記事では、カルシウム拮抗薬の分類ごとの特徴、降圧効果、副作用とその対策、相互作用、そして実際の使い分けの考え方をわかりやすく解説します。
1. まず結論:分類ごとの特徴と使い分けの概要

カルシウム拮抗薬は大きく DHP系(ジヒドロピリジン系) と NDHP系(非ジヒドロピリジン系) に分かれます。
- DHP系(アムロジピン、ニフェジピンCR、シルニジピンなど)
血管平滑筋に作用して血管を拡張させ、強力に血圧を下げます。心拍数への影響は少ないものの、場合によっては反射性頻脈が起こることがあります。主な副作用は足の浮腫、顔のほてり、頭痛など。第一選択になりやすく、特に高齢者や単純高血圧でよく用いられます。 - NDHP系(ジルチアゼム、ベラパミル)
血管拡張作用に加えて、心臓の収縮力や心拍数を抑える作用があります。狭心症や頻脈性不整脈を伴う高血圧で有用。ただし、徐脈や房室ブロックのリスクがあり、心不全や伝導障害がある場合は注意が必要です。ベラパミルでは便秘がよく見られます。
この分類の違いを理解しておくと、患者さんの状態に応じた薬の選択がスムーズになります。
2. 基礎知識:作用機序と分類

カルシウム拮抗薬は、心臓や血管の細胞膜に存在する「L型カルシウムチャネル」をブロックすることで作用します。カルシウムイオンは心筋の収縮や血管の収縮に不可欠ですが、その流入を抑えることで血管が拡張し、血圧が下がります。
分類
- DHP系
主に血管平滑筋に作用し、末梢血管の抵抗を下げます。降圧効果が強く、心拍数への直接作用は少ない。 - NDHP系
血管だけでなく心筋や刺激伝導系にも作用し、心拍数や心収縮力を低下させます。不整脈治療薬としても使われます。
さらにDHP系は世代によって特徴があり、第3世代(アムロジピン、シルニジピンなど)は作用時間が長く、副作用が比較的少ないのが特徴です。
3. 降圧効果と選び方の軸

降圧薬を選ぶ際には、単に「血圧が下がるか」だけでなく、持続時間、副作用リスク、併存症 なども考慮します。
- 持続時間
アムロジピンは半減期が長く1日1回で24時間効果が持続します。これにより服薬アドヒアランス(飲み忘れ防止)が向上します。 - 心拍数や心臓への影響
頻脈や狭心症を伴う場合はNDHP系が有用。逆に徐脈がある患者には避けます。 - 副作用リスク
浮腫が出やすい場合は、ARBやACE阻害薬との併用で改善することがあります。
4. 副作用とその対策

DHP系の副作用
- 足の浮腫:血管拡張によって毛細血管から水分が漏れやすくなります。
対策:併用薬の工夫(ARB/ACE阻害薬)、薬剤の変更。 - 顔のほてり・頭痛:血管拡張によるもの。軽度なら経過観察。
- 歯肉増殖:長期使用でまれに起こります。歯科との連携が重要。
NDHP系の副作用
- 徐脈・房室ブロック:心拍抑制作用による。β遮断薬との併用は慎重。
- 便秘(特にベラパミル):腸管平滑筋の収縮低下による。
- 倦怠感:心拍抑制による循環量低下が原因のことも。
5. 相互作用

- CYP3A4阻害薬(マクロライド系、アゾール系、HIV治療薬など)
→ 血中濃度が上がり副作用リスク増加。 - グレープフルーツジュース
→ CYP3A4阻害により効果増強、副作用増加の恐れ。 - β遮断薬+NDHP系
→ 徐脈・AVブロックリスク。 - P-gp阻害(ベラパミル+ジゴキシン)
→ ジゴキシン中毒のリスク。
6. 症例別の使い分け

- 単純高血圧
→ アムロジピンなど長時間作用型DHPを第一選択に。 - 冠攣縮性狭心症
→ DHP系が有効。β遮断薬単独は避ける。 - 頻脈性不整脈+高血圧
→ NDHP系で心拍数もコントロール。 - 蛋白尿合併高血圧
→ ARBやACE阻害薬に加え、N/T型遮断作用を持つDHPやNDHPを併用。 - 心不全(HFrEF)
→ NDHP系は原則避ける。DHP系を慎重に使用。
7. 服薬指導のポイント

- 飲み忘れたら気づいた時点で服用。ただし2回分は避ける。
- 浮腫が出ても自己判断で利尿薬を増やさない。
- グレープフルーツジュースは控える。
- 動悸や徐脈、めまいがあればすぐに連絡。
まとめ
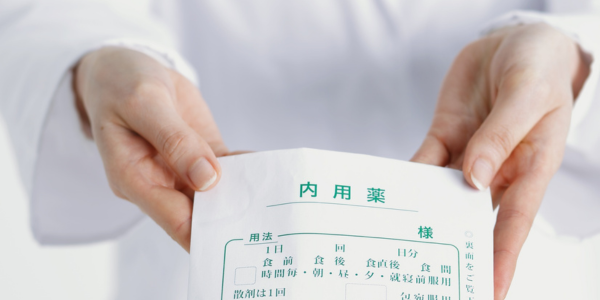
カルシウム拮抗薬は高血圧治療の柱ですが、種類ごとに得意・不得意があります。副作用や相互作用を予測し、患者ごとの背景を踏まえた薬剤選択が重要です。
「分類を知り、適切に使い分ける」ことが、安全で効果的な降圧治療の第一歩です。



コメント