
私たちの腸の中には、数百兆個もの細菌がすんでいます。これは「腸内細菌(腸内フローラ)」と呼ばれ、健康と深く関わっています。近年、この腸内細菌が薬の効き方や副作用にも影響していることが明らかになってきました。特に、がんの治療で注目される「免疫チェックポイント阻害薬(ICI)」という薬では、腸内細菌の状態によって治療の反応が変わることが研究で示されています。
さらに、腸内細菌は薬の吸収・代謝・輸送にも関わることがあり、「同じ薬でも人によって効き方が違う」理由の一つになる可能性もあります。この記事では、腸内細菌と薬の関係について、最新の知見をわかりやすく解説していきます。
腸内細菌とは?

腸内細菌とは、大腸を中心にすんでいる多種多様な微生物のことです。種類は1000種類以上ともいわれ、重さにすると1〜2kg程度。もはや一つの“臓器”のような存在です。
腸内細菌は、食べたものを分解して栄養をつくるだけでなく、
- 免疫(病気と戦う力)の調整
- 代謝(体の中で物質を処理する仕組み)のサポート
- 腸の粘膜バリア(体の中に異物が入らないように守る壁)の維持
といった、重要な働きをしています。
多様性がカギ|腸内細菌のバランスが健康を支える

腸内細菌で特に大切なのは「多様性(diversity)」です。これは、いろいろな種類の菌がバランスよく共存している状態のことです。
たとえば森を想像してください。さまざまな植物や動物が共存している森は環境が安定しています。一方で、一種類だけの植物しかない場所は病気や害虫に弱いですよね。腸の中も同じです。多様性が保たれていると免疫や代謝のバランスも安定しやすく、病気に強い状態になります。
逆に、抗菌薬(細菌を殺す薬)の使いすぎや偏った食生活で菌の種類が減ると、バランスが崩れてしまいます。これを「ディスバイオーシス(腸内環境の乱れ)」と呼び、炎症や感染症、生活習慣病などさまざまな不調の原因になることがあります。
腸内細菌と免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の関係

ICIとは、がん細胞が免疫から逃げる仕組みをブロックする薬です。近年、多くのがん治療で使われていますが、同じ薬を使っても「よく効く人」と「あまり効かない人」がいます。
研究では、この反応の違いに腸内細菌が関わっていることが示されています。たとえば、腸内に特定の菌(例:Bifidobacteriumなど)が多い人ほど、免疫の働きが活発になり、ICIがよく効く傾向が報告されています。また、腸内細菌の「多様性」が高い人では、治療の効果や生存期間が長いというデータもあります。
一方で、ICIの副作用の一つである免疫関連有害事象(irAE)にも腸内細菌が関係している可能性があります。特に腸炎や重度の下痢は、腸内の菌の偏りと関係するという報告が増えています。
抗菌薬の使い方で治療効果が変わる?

ICIの治療中や直前に抗菌薬を使うと、治療効果が下がる可能性があることもわかってきました。抗菌薬は感染症の治療には欠かせませんが、同時に腸内の「よい菌」も減らしてしまいます。特に、ICIを始める前後に広い範囲の細菌を殺す抗菌薬を長く使うと、腸内環境が大きく乱れ、治療の反応率や生存期間が短くなる傾向があると報告されています。
もちろん、感染症を放置することは危険なので、抗菌薬の使用自体が悪いというわけではありません。本当に必要なときに、適切な種類・期間で使うこと(抗菌薬適正使用)が大切です。
腸内細菌と薬の吸収・代謝の関係

腸内細菌は、免疫だけでなく薬の体内での動き(薬物動態:ADME)にも関係しています。
- 一部の薬は、腸内細菌によって活性化されたり分解されたりします。
- 腸内環境が変わると、腸の粘膜やpH(酸性・アルカリ性)、胆汁酸の状態も変わり、薬の吸収量が変化することがあります。
- さらに、腸内細菌が間接的に**肝臓の代謝酵素や薬の運搬たんぱく質(トランスポーター)**の働きに影響することも知られています。
このように、腸内細菌は薬の効き方に直接的にも間接的にも関わっているのです。
どうすれば腸内環境を整えられる?

食事
現時点で最も安全で実践しやすいのは、腸内細菌の多様性を保つ食事です。研究では、食物繊維が多い食事をしている人ほどICIがよく効く傾向があると報告されています。豆類・全粒穀物・野菜・果物をバランスよく摂ることが大切です。
プロバイオティクス(善玉菌のサプリ)
市販のプロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌など)については、効果があるという研究もありますが、逆に自己判断で長期間飲んだ人では「多様性が下がってICIの効き目が悪くなった」という報告もあります。製品によって菌の種類や品質が違うため、一律におすすめできる段階ではありません。主治医や薬剤師に相談しながら慎重に使用することが大切です。
FMT(糞便微生物移植)
腸内細菌を改善する新しい方法として「FMT(糞便微生物移植)」も研究されています。これは、健康な人の便から腸内細菌を取り出して、治療に使う方法です。ICIが効きにくかった患者さんがFMTを受けたあと、治療に反応するようになったという研究もあります。ただし、安全性や標準化がまだ確立していないため、実用化はこれからです。
薬剤師・医療者が現場でできること

- ICIを使う患者では、直近の抗菌薬使用歴やPPI(胃薬)・下剤など腸内に影響する薬のチェックが重要です。
- 抗菌薬を使う場合は、本当に必要かどうかを確認し、広域薬や長期投与はなるべく避ける方向を検討します。
- 食事やサプリの使用について、患者さんにわかりやすく説明し、自己判断での過剰な整腸剤・プロバイオティクス使用を避けるよう助言します。
- 下痢・腹痛・血便などの腸症状が出た場合は、irAE(免疫副作用)・感染・薬剤性を意識して、早めに対応します。
まとめ

腸内細菌は、消化を助ける以外にも免疫反応にも影響することがわかっています。
- がん免疫療法の効き方
- 薬の吸収や代謝
- 副作用の出方
など、多方面で医療に関わる「見えないパートナー」です。現時点では、抗菌薬の適切な使い方と多様性を守る食生活が、腸内環境を整える基本です。今後、FMTや菌叢を使った新しい治療法の研究が進めば、腸内細菌はさらに重要な役割を果たすようになるでしょう。
参考文献・情報源(リンク)
- NCI / MDアンダーソン(Science, 2021):高食物繊維摂取とメラノーマ免疫療法の奏効・PFSの関連。人+マウス研究。https://www.cancer.gov/news-events/press-releases/2021/high-fiber-diet-melanoma-immunotherapy?utm_source=chatgpt.com
- NIH Research Matters(2022):高繊維食が腫瘍増殖を抑制(マウス)。https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/fiber-diet-linked-cancer-immunotherapy-response?utm_source=chatgpt.com
- 抗菌薬とICIのアウトカム:抗菌薬使用とPFS/OS低下の関連(レビュー・観察研究)。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39046682/
- irAEと腸内細菌:ベースライン菌叢と重篤irAEの関連を検討した前向き研究。https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049%2825%2900002-4/fulltext?utm_source=chatgpt.com
- FMTとICI抵抗性:抗PD-1抵抗性メラノーマでFMT+抗PD-1の有望な初期結果。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37414899/
- ファーマコミクロバイオミクス総説(2023–2025):腸内細菌と薬物ADME、ICI応答の概説。https://www.nature.com/articles/s41392-023-01619-w?utm_source=chatgpt.com
- マイクロバイオームとICIの最新レビュー(2025):エビデンスの整理と今後の方向性。https://www.jci.org/articles/view/184321?utm_source=chatgpt.com
- プロバイオティクスの留意点:観察・メタ解析での賛否、過去の警鐘。https://chatgpt.com/c/68e21d32-93dc-8323-9314-50b2d45f7f28?model=gpt-5

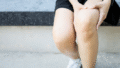
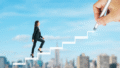
コメント