1. はじめに──薬剤師が「とびひ」を学ぶ意義

夏になると、薬局に「子どもの肌がただれてきた」「虫刺されから広がったような発疹がある」といった相談が急増します。これらの症状の多くは、いわゆる「とびひ(伝染性膿痂疹)」と呼ばれる皮膚の感染症です。
とびひは子どもを中心に感染が広がりやすく、保育園や家庭内で一気に拡大してしまうこともあります。こうした感染症への対応で、薬剤師が果たす役割は非常に重要です。処方薬の適切な使用はもちろんのこと、保護者への説明、感染予防の指導、OTCの対応まで求められます。
本記事では、薬剤師が「とびひ」について体系的に理解できるよう、原因、治療法、指導のポイント、実務上の注意点まで解説します。
2. とびひの基礎知識

2‑1. とびひとは?──定義と病態
「とびひ」とは、細菌によって皮膚の表面に炎症やただれが起こる病気で、正式名称は「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」といいます。
とびひの原因となる主な細菌は以下の2つです:
- 黄色ブドウ球菌:皮膚に水ぶくれ(水疱)をつくりやすいタイプ
- A群溶血性レンサ球菌(溶連菌):皮膚がただれて、かさぶた(痂皮)になるタイプ
傷口や虫刺されなど、皮膚に小さなキズがあると、そこから菌が入り込んで炎症を起こします。皮膚バリアが弱い子どもに多く、かゆみで掻きこわしてしまうことで、他の部位に「飛び火する」ように広がっていくのが特徴です。
2‑2. どんな人に多い?──好発年齢と流行時期
とびひは特に1〜6歳の乳幼児や学童期の子どもに多く見られます。理由は以下のとおりです:
- 肌が薄くてデリケート
- 免疫力がまだ十分でない
- かゆくなると無意識に掻いてしまう
- 手洗いや衛生管理が十分にできないことがある
また、6〜9月の夏場に患者数が急増します。暑くて汗をかきやすく、皮膚が湿った状態が続くと、細菌が繁殖しやすくなるためです。
2‑3. 症状の特徴と診断の仕方
とびひは、主に2種類に分けられます。
| 種類 | 原因菌 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 水疱性とびひ | 黄色ブドウ球菌 | 水ぶくれ→破れて皮がむける(びらん) |
| 痂皮性とびひ | 溶連菌 | ジクジクした膿→乾いてかさぶた(痂皮)に |
診断は医師の視診(見た目)で判断されることがほとんどです。発熱やリンパの腫れがある、症状が治りにくい場合は、皮膚の検査(細菌培養)を行うこともあります。
3. とびひの治療と薬の選び方

3‑1. 外用薬と内服薬の使い分け
とびひの治療は、基本的に抗菌薬(抗生物質)で原因となる菌を退治することが中心です。症状の重さによって使う薬が異なります。
- 軽症(病変が小さく、数も少ない):抗菌薬の外用薬(塗り薬)だけで対応します。
- 中等症以上(病変が広がっている・発熱あり):外用薬と一緒に、内服薬(飲み薬)を併用します。
例えば、セファレキシンやセフジトレンなどのセフェム系抗生物質が内服薬としてよく使われます。
3‑2. 菌に合った薬を使うことが重要
薬剤師として注意すべきは、原因菌と薬の相性(感受性)です。
- 黄色ブドウ球菌(MSSA):多くの第一世代セフェムに感受性あり
- 溶連菌:セフェム系やペニシリン系でよく効く
- MRSA(薬が効きにくい耐性菌):ファロペネム、ホスホマイシンなどの使用が考慮されます
最近では、mupirocin(ムピロシン)に対する耐性が増えてきているため、MRSA保菌者に対する除菌のための鼻腔内塗布にしか保険適応がありません。
3‑3. 投与量・服薬指導の注意点
子どもへの内服薬は、体重に合わせた正確な投与量が必要です。処方監査では、年齢だけでなく体重も必ずチェックしましょう。
また、セフジトレンなどは鉄剤・牛乳と一緒に飲むと吸収が落ちることがあるため、服用タイミングも指導が必要です。
4. 薬剤師の現場対応──処方監査・服薬指導・OTC対応

4‑1. 処方監査でのチェックポイント
- 子どもの体重と処方量が合っているか?
- 外用薬とステロイドを混合する指示がある場合、薬の性質的に混ぜてよいか(混合禁忌)を確認
- 短すぎる投与日数(3日以下)は再診予定の確認が必要
4‑2. 服薬・塗布の説明
外用薬を塗る際には、「どれくらいの量を、どのように塗るのか」をわかりやすく伝えることが重要です。
- FTU(フィンガーチップユニット):指の先から第一関節までの量=大人の手のひら2枚分に相当
- 入浴は「こすらず泡でやさしく洗い、シャワーで流す」が基本
- ステロイド併用時は、「赤み・かゆみが取れたらすぐ中止する」ことも伝えましょう
4‑3. OTC対応での注意点
OTCでの対応はあくまで軽症・初期の段階に限られます。以下のような場合は、受診を促しましょう:
- 水ぶくれやかさぶたが広がっている
- 発熱やぐったりしている
- 兄弟にもうつってきている
OTCとしては、ポビドンヨードや亜鉛華軟膏が使われることもありますが、耐性菌や悪化を防ぐために長期使用は避けるべきです。
5. 感染拡大を防ぐためにできること

5‑1. 日常生活での感染予防
とびひは、皮膚にできた膿や水ぶくれの液体に触れることでうつります。以下のような生活指導が効果的です:
- 爪は短く切る(掻きこわし防止)
- タオルや衣類を共有しない
- 衣類や寝具は60℃以上で洗濯するのが望ましい
5‑2. 登園・登校の目安
保育園や学校では、「すべての発疹がかさぶたになっており、全身状態が良ければ登園可能」とされています。プールについては完全に治癒するまで禁止です。
医師の判断が必要な場合もあるため、自治体ごとのルールも確認し、薬局として情報提供できるようにしておきましょう。
6. ケーススタディ

| ケース | 対応例 |
|---|---|
| 抗生物質にアレルギーがある | ホスホマイシンやマクロライド系抗生物質を医師に提案できるようにする |
| アトピーと併発している | ステロイド+抗菌薬の併用を検討し、保湿剤でスキンケアを併用 |
7. まとめ──薬剤師としての関わり方

- とびひは子どもに多く見られる皮膚感染症で、早期対応と正しい指導が感染拡大を防ぐ鍵になります。
- 薬剤師としては、正しい薬の選択、処方のチェック、塗り方や生活指導まで包括的にサポートする必要があります。
- OTC相談や保護者への説明時には、「3日以内に治らなければ受診を」など明確な指針を伝えることが大切です。
参考URL
とびひとはなんですか?,公益社団法人日本皮膚科学会
伝染性膿痂疹,神奈川県こども医療センター
https://www.radionikkei.jp/uptodate/uptodate_pdf/uptodate-140305.pdf厚生労働省『保育所における感染症対策ガイドライン』2024 年版
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mcip-att/2r9852000002mdgm.pdf薬剤師としての将来に不安があるなら──転職も一つの選択肢
とびひのような季節性疾患に限らず、薬剤師として日々多様な患者さんと向き合う中で、
「もっと専門性を高めたい」
「在宅や小児の領域に強い薬局で働きたい」
「患者対応にゆとりのある環境を探したい」
そんな想いを抱える方も少なくありません。
薬剤師のキャリアには、調剤薬局だけでなく、病院・企業・在宅特化型薬局・小児に強い薬局など、さまざまな選択肢があります。現場に追われる中で、自分に合った働き方を見つけるのは難しいもの。だからこそ、転職エージェントの活用が効果的です。
● 薬剤師の転職に強いエージェントをご紹介
以下のようなエージェントは、薬剤師専門でサポートしており、無料で利用可能です。
- ファル・メイト:派遣やスポット勤務に強く、柔軟な働き方を希望する方に
- メディカルリソース:在宅や小児対応に特化した薬局求人も多数
- アポプラスキャリア:企業求人や地域密着の薬局への転職実績が豊富
- JJメディケアキャリア:地方勤務や高収入求人に強みあり。未経験可の案件もあり
- アイリード:中小薬局や地域密着型で働きたい方向け
📌 どのエージェントも登録は 1分程度で完了し、求人紹介や履歴書添削、面接対策などすべて無料でサポートしてくれます。
転職=ネガティブな選択ではありません。
薬剤師として「もっとこう働きたい」「小児医療を深めたい」という前向きな選択肢として、今の職場を客観視する機会にもなります。


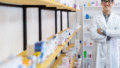
コメント