はじめに

高齢化が進む日本では、高齢者の「ポリファーマシー(多剤併用)」が深刻な問題となっています。最新のガイドラインでは、薬剤の適正使用を進める方針が示されており、薬剤師の役割がますます重要になっています。
この記事では、最新の方針を紹介しながら、薬剤師が現場でできる工夫についてもわかりやすく解説します。
1. ポリファーマシーとは?なぜ問題なのか

ポリファーマシーとは、「必要以上に多くの薬を服用している状態」を指します。特に高齢者は、複数の病気を抱えていることが多く、それぞれに対する薬が処方されるため、薬の種類が自然と増えてしまいがちです。
しかし、薬が増えることにはさまざまなリスクが伴います。たとえば、
- 副作用が出やすくなる
- 薬同士の相互作用で体調が悪化する可能性がある
- 飲み間違いや飲み忘れが増える
といった問題が起こりやすくなります。さらに、必要のない薬を服用し続けることで医療費が増加したり、生活の質(QOL)が低下することもあります。
このような背景から、薬の内容を見直し、より安全で適切な薬物療法を提供するために、薬剤師が介入し、薬の適正使用を支えることが重要です。
2. 最新ガイドラインの概要

高齢者のポリファーマシー対策として、厚生労働省は「高齢者の医薬品適正使用の指針」を公表しました。
このガイドラインでは、高齢者にとって本当に必要な薬だけを使い、不要な薬はできるだけ減らすという考え方が基本になっています。具体的には、次のような方針が示されています。
- まずは薬を「減らす」ことを意識する
→ 薬が多いほど体への負担が大きくなり、副作用のリスクも高まります。そのため、治療効果が低い薬や重複している薬は見直していきましょうという考えです。 - 高齢者の体の状態や生活スタイルに合わせて薬を見直す
→ 年齢とともに肝臓や腎臓の機能が低下し、若い人と同じ薬の量でも効きすぎたり副作用が出たりすることがあります。また、「飲みにくい」「トイレが近くなるので困る」など、日常生活に支障をきたすケースもあるため、一人ひとりに合った調整が大切です。 - 医師・薬剤師・看護師など、チームで連携して支援する
→ 薬の見直しは、医師だけでなく、薬剤師や看護師など複数の職種が協力することで、より安全で効果的に進められます。
さらに、日本老年医学会や日本薬剤師会も、ポリファーマシーの解消に向けて啓発や教育を行っています。
また、海外では次のような基準も広く使われています:
- STOPP/START基準(ストップ・スタート基準)
→ 「STOPP」は高齢者にとって避けるべき薬を、「START」は必要なのに見逃されがちな薬を示したチェックリストのようなものです。 - Beers Criteria(ビアーズ基準)
→ アメリカ老年医学会が作成したガイドラインで、高齢者に使うべきでない薬や注意が必要な薬を一覧にしたものです。世界中の高齢者医療で参考にされています。
こうしたガイドラインや基準を活用しながら、薬を「たくさん使う」のではなく、「本当に必要な薬を、適切な量で、安全に使う」ことが、これからの医療で求められているのです。
3. 薬剤師の役割とは?

ポリファーマシーの対策には、薬剤師の専門知識が欠かせません。
薬剤師は、患者が服用している薬の内容を確認し、
- 飲み合わせに問題がないか
- 同じ効果の薬が重複していないか
- 飲みにくさや副作用の原因となる薬がないか
といった視点から薬の見直しを行えます。
また、医師や看護師など他の職種と連携し、患者にとって最適な薬物療法を提案することも大切です。
4. 現場で薬剤師ができる工夫

薬剤師が現場で実践できる工夫には、次のようなものがあります。
- 服薬カレンダーや一包化の提案
→ いつどの薬を飲めばいいかがわかりやすくなり、飲み忘れを防げます。 - 残薬の確認と整理
→ 飲みきれていない薬がある場合は、その理由を確認し、処方見直しのきっかけになります。 - OTC医薬品やサプリメントの確認
→ 処方薬以外に飲んでいるものとの相互作用リスクも見逃せません。 - 患者や家族との丁寧なコミュニケーション
→ 実際の生活や困りごとを聞くことで、本当に必要な薬だけを選ぶ手助けができます。
これらの取り組みはどれも、患者の負担を減らし、安全に薬を使い続けるために有効です。
5. 今後に向けて薬剤師に求められること

高齢者のポリファーマシー対策を実効性のあるものにするには、薬剤師自身が最新のガイドラインを正しく理解し、それを日々の業務にどう活かすかが重要になります。
たとえば、「この薬は高齢者には副作用が出やすいとされている」といったガイドライン上の知識を、目の前の患者さんの状態と照らし合わせながら使っていくことが求められます。
■ICTやAIの活用も進むなかで必要な力とは?
最近では、ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)を活用して、患者さんの薬の履歴を自動的にチェックしたり、相互作用のリスクを瞬時にアラート表示してくれるシステムも登場しています。
しかし、それだけでは十分ではありません。AIが「この薬の組み合わせは注意が必要」と教えてくれても、
- 実際に患者さんがその薬をどのように飲んでいるか
- 生活スタイルや身体機能にどんな影響があるか
- 飲みたくないという気持ちがあるかどうか
といった“人間的な部分”は、薬剤師の観察力・判断力・コミュニケーション力によって初めて見えてくるものです。
■ガイドラインは「道しるべ」、最終的な判断は薬剤師の経験と対話力
ガイドラインはあくまで「道しるべ」にすぎません。そこには「一般的にこうするのがよい」と書かれていますが、一人ひとりの患者に合った正解は違うこともあります。
たとえば、
- 薬の副作用でふらつきや転倒リスクがある人
- 認知機能が低下していて服薬管理が難しい人
- 一人暮らしで、医療機関へのアクセスが難しい人
といった事情を考慮して、「この薬は今の生活に合っているか?」「減らしても問題ないか?」を見極めるには、やはり薬剤師の専門性と人間力が不可欠です。
今後ますます進む高齢化社会において、薬剤師には「機械では代替できない価値」が強く求められていくでしょう。
6. まとめ

高齢者のポリファーマシーは、命にかかわるリスクをはらむ問題です。最新のガイドラインでは、薬の「適正使用」へのシフトが強く求められています。
薬剤師は、その中心的な役割を担う専門職として、服薬状況のチェックや処方見直し、患者との対話を通じて、ポリファーマシーの解消に貢献できます。日々の小さな工夫が、大きな安心につながります。
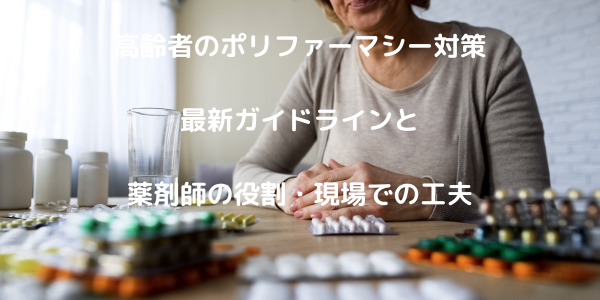
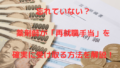

コメント