電子薬歴とは?紙薬歴との違いをわかりやすく解説

薬歴(やくれき)とは、患者さんに薬を渡す際の記録で、服薬指導の内容や副作用の有無などを記載するカルテのようなものです。
従来は紙に手書きで記録していましたが、現在は多くの薬局で「電子薬歴」が使われるようになってきています。
電子薬歴とは、薬歴をパソコンやタブレットなどで管理できるシステムです。記録の入力、検索、保存、共有がすべてデジタル化されており、薬局の業務全体を効率化するツールとして注目されています。
電子薬歴を導入することで得られる7つのメリット
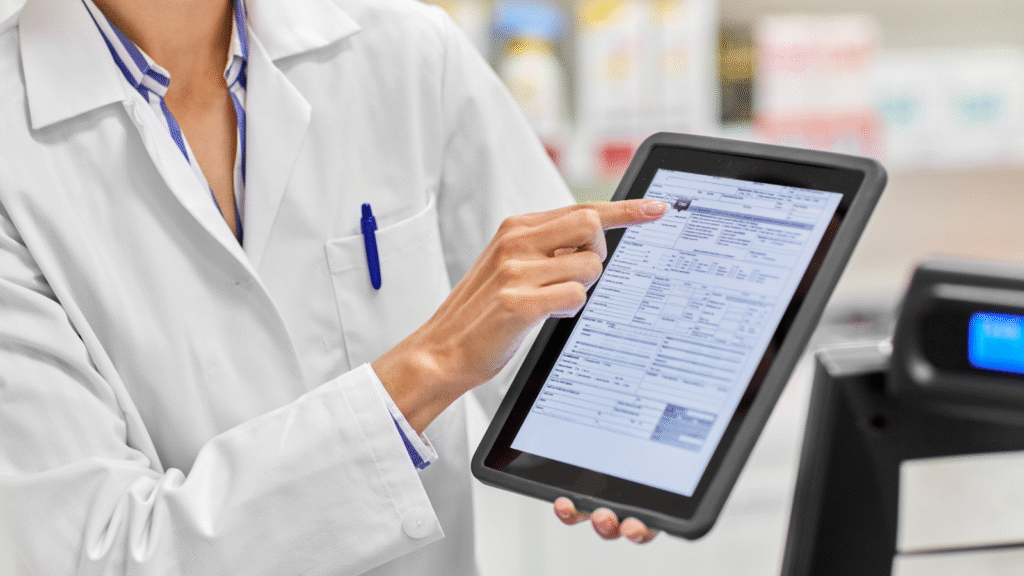
1. 薬歴作成にかかる時間を短縮できる
薬歴を一から手書きするには時間がかかります。患者さんが次々来局する忙しい時間帯には、メモだけ残して後で清書する薬剤師も多いでしょう。
電子薬歴では、音声入力やAIによる自動要約機能を使えば、服薬指導の内容をその場で記録できます。
たとえば、患者さんとの会話を録音し、それをAIが自動的に整理・文章化することで、薬歴作成にかかる手間を減らせます。
実際に、薬樹薬局ではAI入力機能を活用した結果、その場で薬歴を完結できた割合が85%に上がり、薬歴残業がほとんどなくなったと報告されています。
2. よく使う指導内容をテンプレート化できる
薬歴では、「食後に1日3回服用してください」など、よく使う定型表現が多くあります。
電子薬歴では、こうした文章を「テンプレート」としてあらかじめ登録しておけるため、クリックだけで入力可能になります。
さらに、処方された薬に応じて、自動的に関連する指導文や加算項目(服薬支援の点数)が表示される機能もあるため、記録の抜け漏れを防ぐことができます。
3. 患者対応の時間が増える
これまで、薬歴作成に時間が取られて患者さんとの会話が短くなることもありましたが、電子薬歴を活用することで、記録作業にかける時間を減らし、そのぶん患者対応に集中できます。
たとえば、日本調剤では電子薬歴導入後、患者さんの相談時間がしっかり確保できるようになり、服薬指導の質が向上したという声も上がっています。
4. 調剤ミスや見落としの防止に役立つ
電子薬歴には、以下のような安全性を高める機能が搭載されています。
- 併用禁忌のアラート(一緒に飲むと危険な薬を警告)
- 重複投与のチェック(同じ成分の薬が複数処方されていないか)
- 年齢や腎機能による投与量チェック(高齢者への過量投与などを防止)
これらのアラートは、薬剤師が入力する際に自動で表示されるため、ミスを未然に防ぐことができます。
また、記録形式がSOAP(Subjective・Objective・Assessment・Plan)で統一されており、医師や看護師と連携する際にも読みやすく、情報共有しやすいのも特長です。
5. 在宅訪問や災害時にも強い
電子薬歴は、パソコンだけでなくタブレットやスマホからもアクセスできるため、在宅患者の訪問指導時や緊急対応時にも柔軟に使えます。
また、クラウド型の電子薬歴ではデータが外部のサーバーに保管されているため、地震や水害などの災害が起きたときでもデータが消えにくいという安心感があります。
6. 法令・制度への対応がしやすい
2023年から本格導入された電子処方箋に対応しているシステムでは、処方情報と調剤結果を電子的に記録し、国が定める保存期間(5年間)に沿って安全に保管できます。
紙では保存や検索が大変だった記録も、電子薬歴と連携すればワンクリックで提出可能になるため、監査や個別指導への対応もスムーズです。
7. 薬局経営にも好影響
電子薬歴は単に業務を効率化するだけでなく、薬局の経営改善にもつながります。
| 効果 | 内容 |
| 人件費の削減 | 薬歴作成時間が短くなることで、残業が減り、給与コストが抑えられる |
| 加算取得がしやすい | トレーシングレポート(服薬後フォロー)や服薬支援の記録漏れが減少 |
| 補助金制度の対象 | IT導入補助金では、最大80万円の助成を受けて導入費を抑えられるケースも |
| 業務データの可視化 | 疑義照会率、薬歴完了率、指導加算取得率などを自動集計し、店舗運営に活用可能 |
導入前に確認したいポイントとステップ
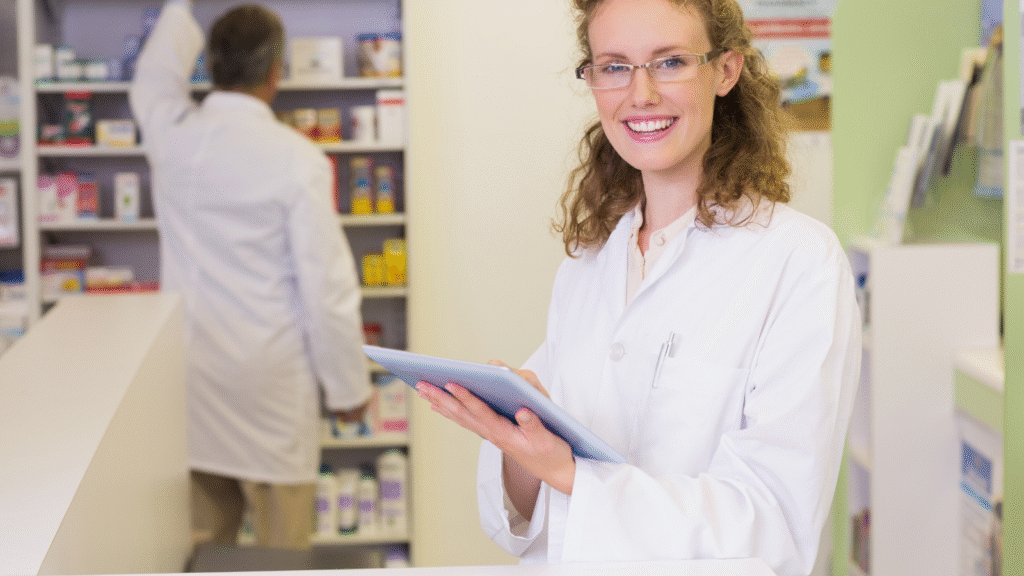
電子薬歴の効果を最大限に引き出すには、導入前の準備が重要です。以下の手順で進めるとスムーズです。
ステップ1:現在の業務を見える化
まずは、薬歴作成に何分かかっているのか、患者の待ち時間はどのくらいか、残業がどのくらい発生しているかなど、現場の「時間の使い方」を把握しましょう。
ステップ2:システム選び
電子薬歴には「クラウド型」「オンプレミス型」があります。
- クラウド型:インターネット環境があればどこでも使える。アップデートも自動。
- オンプレミス型:院内サーバーに設置。セキュリティは高いがコストも高め。
ほかにも、AI音声入力、電子処方箋連携、レセコンとの連動ができるかなどもチェックポイントです。
ステップ3:試験的に導入して効果を測る
いきなり全店舗に導入するのではなく、1店舗で試験運用し、薬歴完了率や患者満足度の変化を確認すると、効果が見えやすくなります。
ステップ4:スタッフ研修は実践形式で
操作マニュアルだけでなく、ロールプレイや実際の患者対応を想定した練習を取り入れると、現場での活用がスムーズになります。
活用のコツと注意点

効率化のコツ
- マイテンプレート登録:疾患や薬剤別に定型文を登録し、クリックだけで入力。
- 音声入力の精度アップ:ノイズキャンセリング付きマイクを使うと認識ミスが減ります。
- 成功事例の共有:月ごとの薬歴完了率や指導加算取得率をスタッフで共有すると、全体の質が上がります。
注意したい点
| 課題 | 対策 |
| AIの要約ミス | 薬剤師の最終確認を必ず行い、誤記載を防ぐ |
| ネット接続の不具合 | 予備回線やオフライン入力モードの準備を |
| 紙業務の踏襲で終わる | 単なる置き換えではなく、フローそのものを見直すことが重要 |
まとめ:電子薬歴は薬局の“働き方”そのものを変えるツール
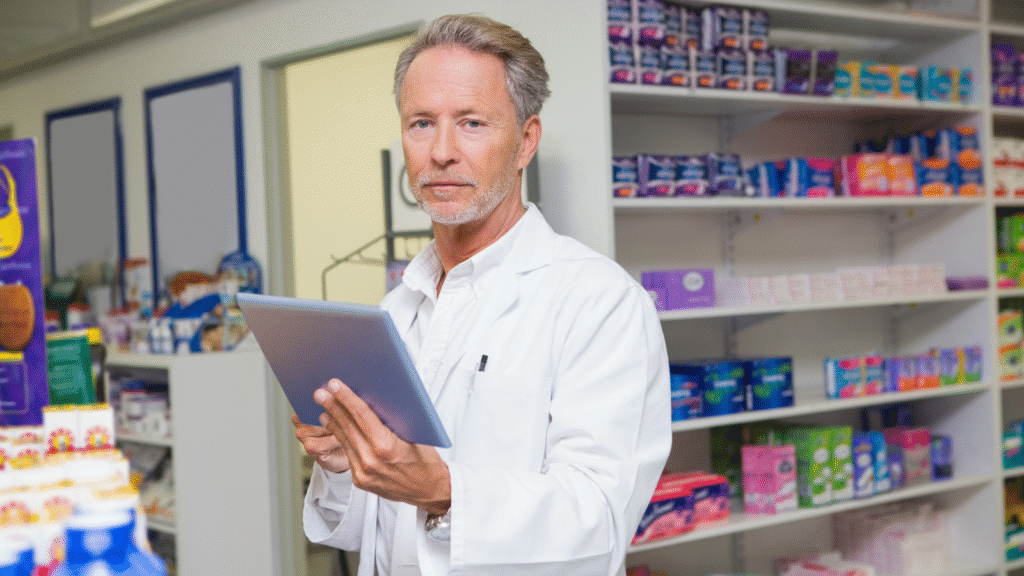
電子薬歴は単なる「紙のデジタル化」ではありません。
それは、薬剤師が“人にしかできない業務”に集中するための強力なサポートツールです。
- 薬歴作成の時間短縮
- 患者との対話時間の確保
- 調剤ミスの防止
- 経営指標の見える化
- 災害時対応や制度順守への対応
これらを同時に実現できる可能性があるのが電子薬歴の強みです。
まずは小さな一歩から。
1店舗での導入テストから始め、操作に慣れることで、徐々に全体の業務改善へとつながります。
参考URL:https://site.solamichi.com/news/20250602
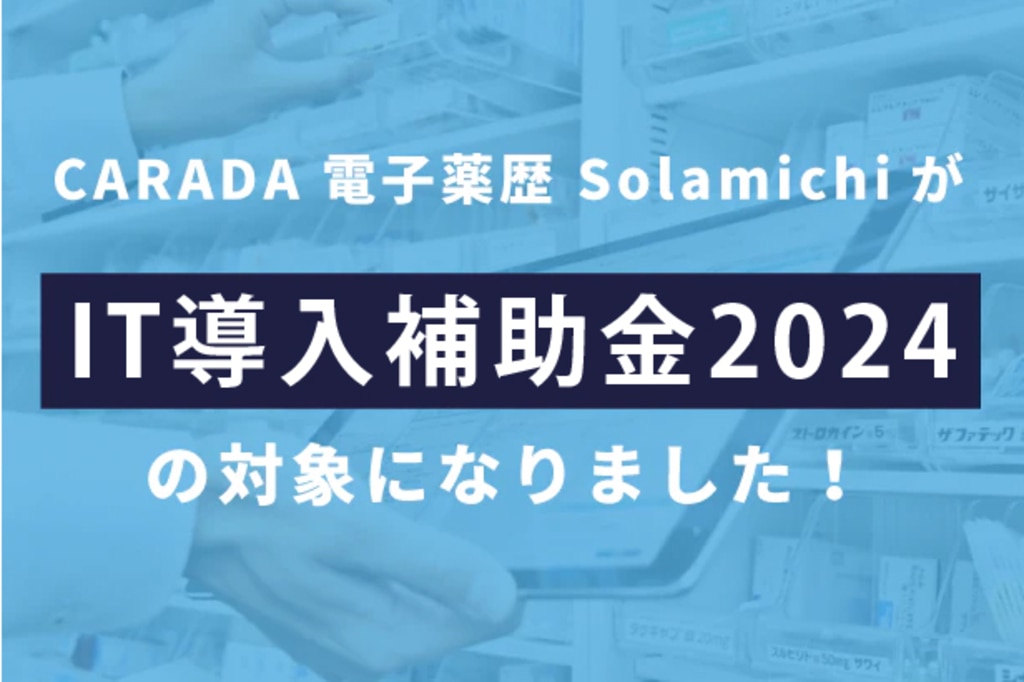
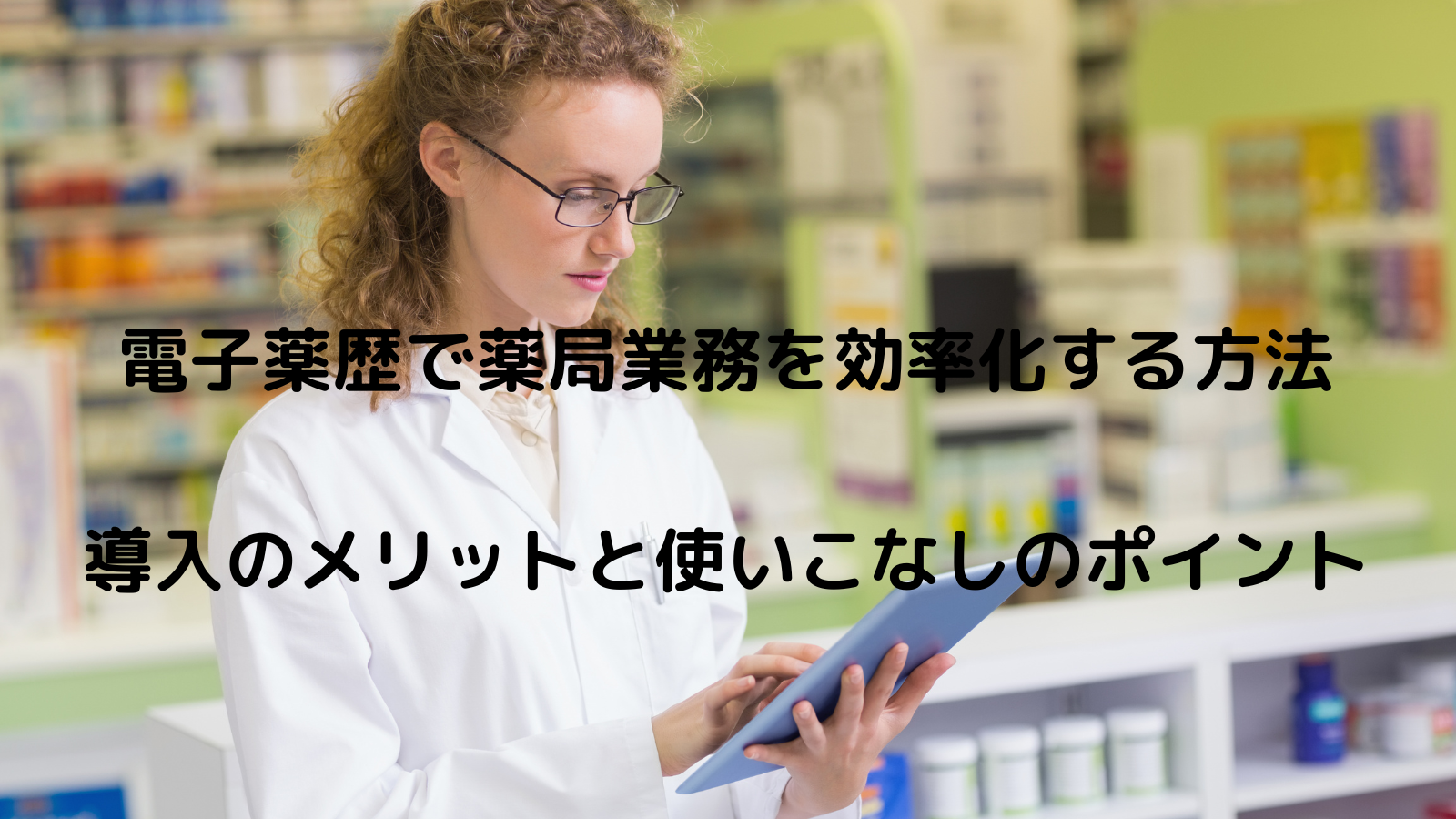

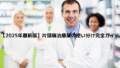
コメント