はじめに|リフィル処方箋導入の背景

近年、医療現場では「医師の働きすぎ」や「病院の混雑」が社会問題になっています。
これを解決する方法の一つとして登場したのが「リフィル処方箋」という仕組みです。
2022年4月から正式にスタートし、病院やクリニックで使われるようになりました。患者さんが毎回病院に行かなくても薬を受け取れるようになるため、通院の手間や医療費の削減が期待されています。
リフィル処方箋制度の概要

定義と基本ルール
リフィル処方箋とは、1枚の処方箋で同じ薬を最大3回までもらえる制度のことです(初回+2回)。
通常の処方箋は1回しか使えませんが、リフィル処方箋があれば、医師の再診がなくても薬局で薬を受け取れます。
ただし、いくつかのルールがあります:
- 初回の調剤(1回目)は、処方箋が発行された日から4日以内に薬局で受付しなければなりません。
- 2回目以降は、医師が指定した「次回調剤予定日」の前後7日間の間に受け取れます。
- 紛失したり期限を過ぎてしまうと、たとえ回数が残っていても使えなくなります。
制度の目的と期待される効果
この制度によって得られるメリットは多くあります。
- 患者さんは毎回病院に行く必要がなくなるため、時間も交通費も節約できます。
- 医療機関も再診の回数が減ることで、外来の混雑を防ぎ、他の患者さんに手厚い医療を提供できます。
- 薬剤師も、患者さんの健康状態を継続的にフォローしやすくなるメリットがあります。
適用対象と除外薬

適用されるケース
リフィル処方箋は、症状が安定していて長期的に同じ薬を使う患者さんが対象です。
たとえば、次のような病気に使われる薬は対象になります:
- 高血圧症(血圧の薬)
- 脂質異常症(コレステロールを下げる薬)
- 2型糖尿病(血糖を調整する薬)
適用されないケース
以下のような薬はリフィル処方箋では使えません。
- がん治療薬や免疫を抑える薬(副作用が強いため)
- 麻薬や向精神薬など、厳しい管理が必要な薬
- 14日までしか処方できない薬(例:小児の風邪薬など)
また、薬を使い始めたばかりのときや、薬の量を調整している期間中もリフィルは使えません。
処方箋の書式と有効期間
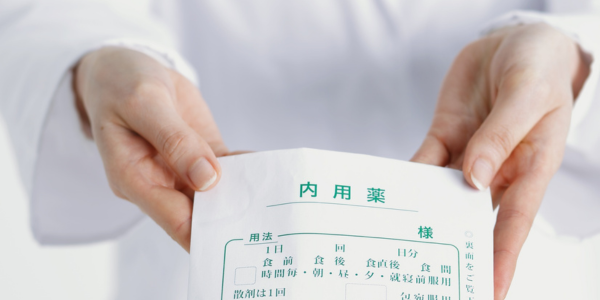
リフィル処方箋には、医師が以下の情報を記載する必要があります。
- 「リフィル可」と明記されたチェック欄
- 「残り回数」が数字で書かれている(例:あと2回)
- 「次回の薬を受け取る予定日」
患者さんはこの処方箋をなくさないように保管しておく必要があります。
期限が切れたり紛失すると、たとえ残り回数があっても使えなくなりますので注意が必要です。
2024–2025 年診療報酬改定のポイント

2024年と2025年には、リフィル処方箋の制度がさらに使いやすくなるように見直されました。
- 2024年の改定では、病院や薬局がリフィルを使いやすくなるよう請求方法が簡略化されました。
- 2025年には、リフィルを広く使ってもらうため、政府の方針(骨太方針)にも重点施策として記載されました。
また、2023年からスタートした「電子処方箋」でも、リフィル処方箋が使えるようになりました。
これにより、薬局間での情報共有やリマインド通知などがしやすくなり、患者さんの飲み忘れ防止にもつながっています。
薬局での実務対応フロー

受付時の確認ポイント
薬剤師は、患者さんがリフィル処方箋を持ってきた場合に、以下の点をチェックします:
- リフィル可能な処方箋かどうか
- 残り回数があるか
- 調剤予定日の範囲内か
- 対象薬かどうか(除外薬でないか)
服薬指導・フォローアップ
薬を渡すときは、次のような情報をわかりやすく伝えることが大切です:
- 次に薬を受け取る時期
- 薬の保管方法や副作用の注意点
- 体調が変わったときは、回数が残っていても必ず医師に相談すること
また、次回来局日を患者さんのスマホにリマインドすることで、薬の飲み忘れや取り忘れを防ぐ工夫も効果的です。
患者教育で伝えるべき注意点

患者さんにとって、リフィル処方箋は便利な制度ですが、注意しなければならないこともあります。
- 処方箋をなくした場合は使えなくなる → 写真を撮っておくのがおすすめ
- 症状に変化があったときは、回数が残っていても自己判断で薬を続けず、受診する
- 「次回調剤予定日」はカレンダーアプリなどで管理すると安心
まだ制度を知らない人も多く、患者の約4割が「リフィル処方箋を知らない」と回答した調査もあります。
そのため、薬剤師からの丁寧な説明が大切です。
制度活用のメリットと課題

メリット
- 通院回数が減ることで、患者さんの時間や費用の負担が軽減されます。
- 医療機関も外来の混雑が減り、効率的な診療ができます。
- 国全体の医療費も削減できると期待されています(年間150億円規模との試算もあります)。
課題
| 課題 | 現状 | 薬局でできること |
|---|---|---|
| 制度の認知度が低い | 多くの患者がリフィルを知らない | ポスター掲示、薬局での声かけ、SNS発信 |
| 報酬が少ない | 薬局側のインセンティブが低い | 情報共有と効率化で負担軽減 |
| システム整備が必要 | 電子薬歴やPOSとの連携が課題 | 補助金の活用や業者との連携が重要 |
今後の展望と薬剤師への提言

リフィル処方箋は、今後さらに活用が進むと考えられています。
たとえば、
- 高齢者や在宅患者への訪問服薬指導にも応用可能
- 血圧や血糖値の自己測定と連携することで、より安全な薬の管理が可能
- 電子化やICTの導入によって、薬局の業務も効率化されます
薬剤師がリフィル処方箋を正しく理解し、患者さんに丁寧に説明することが、制度の成功に不可欠です。
まとめ

リフィル処方箋は、患者・医療機関・薬局すべてにとってメリットがある制度です。
今後ますます利用が広がることが予想される中、薬剤師としてこの制度をしっかり理解し、活用することで、患者さんの健康維持と医療の効率化に貢献できます。
また、制度対応の知識はキャリアにも直結します。
在宅医療やリモート対応など、新しい働き方に対応できるスキルとして注目されており、今後の転職や独立にも役立つ可能性があります。
参考URL
厚生労働省広報誌「導入から2年超 使おう! リフィル処方箋」2024 年 10 月号
政府広報オンライン「リフィル処方箋を知っていますか?」2024 年 11 月

PHC メディコムコラム「電子処方箋×リフィル処方箋」2023 年 12 月

日本ジェネリック医療情報コラム「骨太方針 2025 とリフィル普及」2025 年 7 月

厚労省「長期処方・リフィル処方箋の実施状況調査報告書」2024 年度



コメント