医薬品の“添加物”はなぜ入っているのか

薬を飲むとき、多くの人が注目するのは「有効成分(効き目のある成分)」です。しかし実際には、薬にはそれ以外の「添加物」もさまざま含まれています。
「添加物って体に悪いものでは?」と不安に感じる方も少なくありませんが、医薬品の添加物は薬の品質や使いやすさを支える、とても重要な役割を担っています。
食品の添加物と混同されることもありますが、医薬品の添加物は法律や基準に基づいて厳密に管理されており、「余計なもの」ではなく、薬の“設計”に欠かせない要素です。
添加物の基本:定義と主な役割

医薬品の添加物とは、有効成分以外で、薬を作るときや使うときに必要な成分のことです。薬の形を整えたり、安定性を保ったり、味を良くしたりするために使われます。
代表的な機能
- 賦形剤(ふけいざい):有効成分が少量でも錠剤やカプセルにできるよう、かさを増やす成分(例:乳糖、デンプンなど)
- 結合剤:粉がバラバラにならないよう、形を固める成分(例:ポビドン)
- 崩壊剤:錠剤を飲んだあと、胃や腸で速やかに崩れるようにする成分
- 滑沢剤:製造時に錠剤が機械にくっつかないようにする成分(例:ステアリン酸Mg)
- コーティング剤:錠剤の表面を覆い、苦みを隠したり胃で溶けにくくしたりする成分
- 溶媒・緩衝剤・保存剤:注射液や点眼薬などで、pHを整えたり、細菌の繁殖を防いだりする目的で使われます。
これらの添加物があるからこそ、薬は安定して効果を発揮し、飲みやすい形で患者さんに届けられます。
剤形別にみる添加物の使われ方

薬の剤形(形)によって、使われる添加物の種類や役割は少しずつ異なります。
錠剤・カプセル
錠剤には賦形剤・結合剤・崩壊剤・滑沢剤・コーティング剤などが組み合わされています。崩壊剤が入っているおかげで、飲んだあと速やかに溶け、有効成分が体に吸収されます。
散剤・顆粒・シロップ
小児用の薬では、味や飲みやすさの調整が重要です。甘味料や香料、粘度を高める添加物が使われ、苦みをマスクしたり、飲みやすくしています。
外用薬(軟膏・クリーム・ゲル・貼付剤)
外用薬では「基剤」と呼ばれる添加物が主役です。軟膏やクリームの塗り心地や薬の放出速度は、この基剤によって大きく変わります。貼付剤では粘着性や皮膚刺激性の調整にも使われます。
注射剤・点眼・吸入薬
注射薬や点眼薬では、薬の安定性や細菌汚染防止のため、防腐剤や緩衝液、等張化剤が使われます。特に点眼薬では、ベンザルコニウム塩化物などの防腐剤が一般的ですが、防腐剤フリー製剤も増えています。
よく使われる添加物と特徴

- 乳糖:代表的な賦形剤。乳糖不耐症の人でも、通常の錠剤に含まれる量では症状が出ないことがほとんどです。
- デンプン・セルロース:崩壊剤や賦形剤として多くの錠剤に使用。
- ポビドン・ヒドロキシプロピルセルロース:結合剤やコーティング剤として使われます。
- ステアリン酸Mg・タルク:滑沢剤として錠剤の製造を助けます。
- ポリソルベート80・PEG・プロピレングリコール:溶媒や可溶化剤として注射薬などで活躍。
- 安息香酸Na・パラベン類・ベンザルコニウム塩化物:防腐剤。細菌汚染を防ぐ役割があります。
- シクロデキストリン:水に溶けにくい薬を溶けやすくするために使われます。
安全性とリスクコミュニケーション

医薬品の添加物は安全性が十分に確認されたうえで使用されています。ただし、まれにアレルギーや不耐症を起こす人もいます。
例えば、タートラジン(黄色の着色料)やポリソルベートにアレルギーを持つ人がいることが知られています。乳糖不耐症の人では、大量の乳糖を摂ると下痢などが起こることがありますが、錠剤に含まれる量はごく少量です。
大切なのは、「含まれているかどうか」だけでなく「どれくらいの量が含まれているか」という視点です。必要以上に不安をあおらず、科学的な根拠に基づいて説明することが大切です。
特定患者での配慮ポイント

- 小児:甘味料や香料、溶媒などによって味や飲みやすさが左右されます。プロピレングリコールやエタノールは、大人と比べて代謝が遅いため、含有量に注意が必要です。
- 妊娠・授乳:基本的には添加物量は少ないですが、防腐剤や溶媒の曝露については添付文書で確認を。
- 高齢者・腎肝機能障害:体内に溶媒や電解質が蓄積しやすくなる場合があるため注意が必要です。
- 宗教・菜食主義・アレルギー:ゼラチン(豚・牛由来)や大豆レシチンなど、由来原料にも配慮が必要なケースがあります。
後発品で“効き目が違う”と感じるのはなぜ?

ジェネリック医薬品(後発品)に切り替えたとき、「なんとなく効き目が違う」と患者さんが感じることがあります。
これは有効成分の量が違うわけではなく、添加物や製剤設計の違いによって、薬の溶け方・味・服用感が変わることがあるためです。
例えば、OD錠(口腔内崩壊錠)の崩れ方やコーティングの有無によって、口の中の感触や胃への刺激が異なることがあります。薬剤師としては、「違いはあるが有効成分は同じ」「様子を見て問題があれば戻すことも可能」という説明が有効です。
現場で起きやすいケースと対応

- 粉砕・経管投与:腸溶錠や徐放錠を砕くと、本来の溶出設計が崩れ、有効成分の吸収が変わったり、副作用が強く出たりすることがあります。添加物が徐放や胃酸耐性を担っているケースも多く、注意が必要です。
- 点眼薬の防腐剤切替:長期点眼で角膜障害を起こす可能性があるため、防腐剤フリー製剤が選ばれることがあります。保存方法や使用期限の説明も忘れずに行いましょう。
- アレルギー・不耐相談:患者さんから添加物に関する相談を受けたときは、添付文書やインタビューフォームで確認し、代替薬の提案や医師への照会を行います。
どう調べる?一次情報の探し方
添加物は、次のような資料で調べることができます。
- 添付文書:添加物欄に一覧が記載されています。
- インタビューフォーム:どのような目的で使われているか、製剤設計の詳細がわかります。
- 日本薬局方:添加物の規格や試験法が定められています。
- FDA Inactive Ingredient Database:海外製剤の情報を調べる際に有用です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 食品添加物がダメでも薬は飲める?
→ 用途・基準が異なります。薬に含まれる量はきわめて少なく、安全性が確認されています。 - Q. 乳糖不耐症でも乳糖入り錠剤は大丈夫?
→ 多くの場合は問題ありませんが、心配な場合は医師や薬剤師に相談を。 - Q. 着色料なしの薬は選べる?
→ 一部に無着色製剤がありますが、対応していない薬剤が大半なので注意が必要です。医薬品に使われる着色料が基準を満たしたものなので、長期間服用しても影響は少ないです。 - Q. 後発品にしたら胃がムカムカする…
→ 添加物やコーティングの違いによることがあります。症状が続く場合は先発医薬品に戻すことも検討してください。
まとめ:添加物は“薬の働きを支える設計”

医薬品の添加物は、薬の形・安定性・安全性・使いやすさを支える大切な存在です。
「入っている=悪い」ではなく、「なぜ入っているのか」「どのくらいの量か」を正しく理解することが、不要な不安を減らす第一歩になります。
薬剤師としては、添付文書やIFを活用して正確な情報を把握し、患者さんの不安や疑問にわかりやすく答えることが重要です。

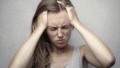
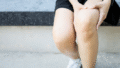
コメント