はじめに──なぜ「がん×漢方薬」が注目されているのか

がん治療の進歩によって、延命効果や治癒率は向上しています。しかしその一方で、抗がん剤や放射線治療による副作用は、患者さんの生活の質(QOL)に大きな影響を与えることがあります。たとえば、強い倦怠感、食欲不振、抑うつ、不眠などは、治療継続の障壁になることさえあります。
こうした背景から、近年では「全人的医療」の一環として漢方薬への注目が高まっています。特に、エキス製剤による処方が一般化し、保険診療の中で活用できるケースが増えている点も注目すべきポイントです。
漢方薬ががん治療で選ばれる3つの理由

1. 全身を整える「総合治療」の考え方
西洋薬が疾患そのものに対する「標的治療」を目指すのに対し、漢方薬は「全身状態」や「体質」を整えるアプローチです。免疫力や消化吸収機能、精神状態など、がん患者の“つらさ”に直接対応する柔軟性が評価されています。
2. エビデンスの蓄積
近年では、漢方薬の薬理作用や臨床効果についての研究も進み、たとえば六君子湯が消化管ホルモン「グレリン」を刺激して食欲を改善する効果があることが明らかになっています。
3. 医療保険での対応が可能
漢方エキス製剤は、診療報酬点数上で「一般薬剤」と同様に扱われるため、特定の症状があれば保険診療の範囲で使用できます。煎じ薬よりも患者の服薬アドヒアランスを確保しやすい点も利点です。
副作用別|がん治療でよく使われる漢方薬の例

がん治療に伴う副作用は多岐にわたりますが、それぞれに対して経験的かつエビデンスに基づいた漢方薬の処方が行われています。
| 副作用・症状 | 使用される漢方薬 | 主な作用・効果 | 備考 |
| 食欲不振・悪心 | 六君子湯 | グレリン分泌促進による食欲改善 | 消化器がん患者での使用報告多数 |
| 倦怠感・全身の疲れ | 補中益気湯 | 気力・体力を補う、免疫賦活 | ホルモン療法後の疲労対策にも |
| 術後・化学療法後の体力低下 | 十全大補湯 | 造血促進、全身倦怠改善 | 骨髄抑制対策としても注目 |
| 抑うつ・イライラ・不眠 | 抑肝散 | 精神安定作用、GABA調整 | 抗うつ薬との併用に注意 |
| 小児がんの支持療法 | 小建中湯 | 胃腸症状の改善、鎮痛補助 | 甘く服用しやすい |
これらの漢方薬は、西洋医学では対応しきれない「つらさ」に焦点を当てた処方であり、症状に応じて柔軟に選択できます。
漢方薬を使う際の注意点|薬剤師が押さえておきたいポイント

漢方薬は「自然由来」だから安心という誤解もありますが、れっきとした「薬」であり、副作用や相互作用も存在します。
1. 相互作用への配慮
柴胡剤(小柴胡湯など)は、インターフェロンや免疫抑制薬との併用で肝障害が報告されています。また、甘草含有製剤では低カリウム血症や血圧上昇に注意が必要です。
抗凝固薬(ワルファリンなど)との併用では、PT-INRの変動も報告されており、モニタリングが欠かせません。
2. 患者背景に応じた適応判断
高齢者や腎・肝機能低下患者、小児、妊婦では慎重投与が求められます。体力や体質を踏まえた薬剤選定と、効果判定のための観察が重要です。
3. 服薬指導と剤形の工夫
煎じ薬は患者の手間が大きいため、エキス製剤が一般的です。ただし、漢方独特の風味や匂いが服薬アドヒアランスに影響することもあるため、服薬の工夫(オブラート、冷やして飲むなど)を提案することも必要です。
エビデンスと臨床現場の融合:最新の研究と症例紹介

六君子湯のグレリン刺激作用
国立がん研究センターでは、六君子湯がグレリン分泌を促進し、化学療法中の食欲低下に効果があるという研究が進められています。
補中益気湯による倦怠感改善
前立腺がん患者に対するホルモン療法後の倦怠感に、補中益気湯の有効性を示した国内の症例報告もあり、特に疲労スコア(CFS)で改善が確認されています。
支持療法としての位置づけ
厚生労働省や学会資料では、がんの支持療法における漢方薬の使用が「エビデンスに基づいた選択肢」として紹介され始めており、今後ますます臨床活用の場が広がると考えられます。
よくある質問(Q&A)

Q:漢方薬はどのくらいで効果が出ますか?
A:体質にもよりますが、1〜2週間で症状に変化を感じる患者さんもいます。継続的な服用と観察が大切です。
Q:市販の漢方薬でも効果は期待できますか?
A:処方と同じエキス製剤でも、使用タイミングや組み合わせによって効果が異なります。特に抗がん剤との併用時は、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
Q:副作用はありますか?
A:あります。たとえば甘草による偽アルドステロン症や、柴胡による肝機能障害などが知られています。体調変化を見逃さず、モニタリングが重要です。
まとめ──がん治療と漢方薬は“対立”ではなく“補完”

がん治療における漢方薬の活用は、決して「西洋医学への対抗手段」ではありません。むしろ、患者さんの体力や精神面を支える「補完的存在」として、西洋医学と併用されるべきものです。
薬剤師はその橋渡し役として、漢方薬の正しい使い方、副作用のモニタリング、他剤との相互作用の確認を行い、チーム医療の中で大きな役割を担います。患者さんのQOL向上に貢献するためにも、今後さらに漢方への理解と活用が求められるでしょう。
参考文献・情報源
- がん治療の副作用軽減ならびにがん患者のQOL向上のための漢方薬の臨床応用とその作用機構の解明
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/22523¥ - 皆川倫範ほか. 「エンザルタミド導入後倦怠感に対する補中益気湯の有効性」『日本泌尿器科学会誌』110巻2号https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjurol/110/2/110_86/_pdf?utm_source=chatgpt.com
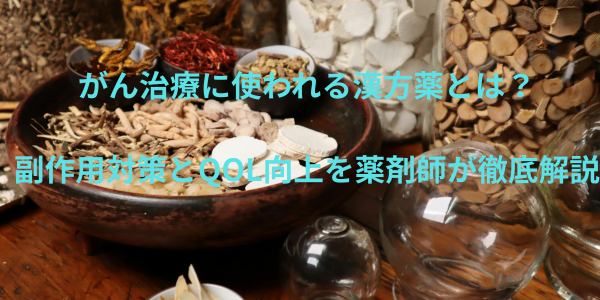
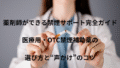
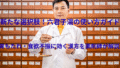
コメント