
PPI(プロトンポンプ阻害薬)は、逆流性食道炎(GERD)や胃・十二指腸潰瘍、NSAIDs潰瘍の治療・予防、Helicobacter pylori(ピロリ菌)の除菌療法など、消化器疾患の治療で非常に頻繁に使われる薬です。
日本で使われているPPIには、オメプラゾール・エソメプラゾール・ランソプラゾール・ラベプラゾールの4種類があり、それぞれに特徴があります。
さらに近年は、PPIとは異なる作用機序を持つP-CAB(カリウムイオン競合型胃酸分泌抑制薬)のボノプラザン(商品名:タケキャブ)が登場し、酸関連疾患の治療選択肢が広がっています。
この記事では、PPIとP-CABの基本的な違い、薬剤ごとの特徴、病態別の使い分け、相互作用や安全性のポイントを解説します。
PPIとP-CABの基本的な違い

PPIは、胃の壁にある「プロトンポンプ」を不可逆的に阻害することで胃酸の分泌を抑えます。
効果が出るまでに1〜3日ほどかかり、プロトンポンプが食事によって活性化したタイミングで結合するため、服用のタイミングが重要です。基本的には朝食の30分前に内服することで最大の効果を発揮します。
一方、P-CAB(ボノプラザン:タケキャブ)は、カリウムと競合してポンプを可逆的かつ強力に抑制します。PPIのように「活性化を待つ」必要がないため、初回から安定した酸抑制効果が得られます。
また、食事の影響が小さいため、PPIのように厳密に食前に飲む必要はなく、毎日同じ時間に内服すれば効果が安定します。
薬剤ごとの特徴(一覧)

まず、各薬剤の基本的な違いを表でざっくり確認しておきましょう。
| 薬剤名 | 酸抑制の強さ | CYP2C19の影響 | 相互作用 | 飲み方 | 特徴 |
| オメプラゾール | 標準 | 受けやすい | クロピドグレルなどに注意 | 朝食前 | 汎用性・コスト◎、相互作用は多め |
| エソメプラゾール | やや強め、個体差少 | 少なめ | クロピドグレル注意は相対的に小 | 朝食前 | 再現性が高く夜間酸にも強い |
| ランソプラゾール | 強め、立ち上がり早い | 受けやすい | テオフィリンなどに注意 | 朝食前 | 除菌療法の実績豊富、OD錠あり |
| ラベプラゾール | 強め、初期反応良 | 低め | 相互作用少なめ | 食事の影響が比較的少 | 多剤併用でも使いやすい |
| ボノプラザン(タケキャブ) | 非常に強い、初回から安定 | 受けにくい(CYP3A代謝) | CYP3A阻害/誘導薬・pH依存吸収薬に注意 | 毎日同じ時間 | PPI不応例・夜間症状・除菌に有用 |
各薬剤の詳しい特徴

オメプラゾール(Omeprazole)
日本で最も古くから使われているPPIで、「PPIの基本形」と言える薬です。長年の実績とジェネリック医薬品の豊富さから、コスト面のメリットがあります。
一方で、CYP2C19という肝臓の酵素で代謝される割合が高く、遺伝的な代謝能力の違いによって効果にばらつきが出やすい点が注意点です。代謝が早い人では効きが悪くなることがあります。
また、クロピドグレル(抗血小板薬)との相互作用が知られており、併用によりクロピドグレルの抗血小板作用が弱まる可能性があります。そのため、併用が必要な場合は他剤への切り替えや時間をずらす対応が行われます。
基本的なGERDや潰瘍治療で、特別な併用薬がない症例では今でも使用頻度が高い薬です。
エソメプラゾール(Esomeprazole)
オメプラゾールのS体(光学異性体)であり、代謝のばらつきが少なく、血中濃度が安定しやすいのが特徴です。
そのため、オメプラゾールよりも効果の再現性が高く、同用量で酸抑制作用がやや強い傾向があります。
夜間の酸分泌抑制にも優れており、夜間に胸やけが強いGERDの患者などでは特に有用です。クロピドグレルとの相互作用はゼロではありませんが、オメプラゾールよりは影響が小さいとされています。
重症の逆流性食道炎や夜間症状が強い患者、安定した効果を求めたい症例に向いています。
ランソプラゾール(Lansoprazole)
酸抑制効果が強く、効果の立ち上がりが早いPPIです。
日本ではH. pylori除菌療法で長く使われてきた実績があり、臨床現場でもなじみ深い薬です。
OD錠(口腔内崩壊錠)があり、水なしで服用できるため、嚥下が難しい患者や高齢者でも使いやすいという特徴があります。
一方、CYP2C19による代謝を受けるため、オメプラゾールと同様に個人差が出る場合があります。また、テオフィリンなどとの相互作用に注意が必要です。
除菌療法や効果を早く出したいケース、OD錠を希望する患者などで活躍します。
ラベプラゾール(Rabeprazole)
CYP2C19による代謝の影響が少なく、効果の個人差が小さいPPIです。
PPIの中では食事の影響も受けにくく、実際の診療で非常に「扱いやすい」薬といえます。
相互作用も少なく、多剤併用の患者にも適しています。
高齢者や併用薬が多い患者、代謝にばらつきがある患者などに向いています。
ボノプラザン(タケキャブ:Vonoprazan)
P-CABという新しい分類に属する薬です。プロトンポンプに対してカリウムと競合することで、初回から強い酸抑制効果を発揮します。
PPIのように食前に飲む必要がなく、毎日同じ時間に内服すれば効果が安定するため、飲み方の自由度が高いのも利点です。
代謝はCYP3Aで行われるため、CYP2C19の個人差の影響はほとんど受けません。PPIで効果が十分に得られなかった患者にも有効な場合があります。
一方で、CYP3A阻害薬・誘導薬(クラリスロマイシン、アゾール系抗真菌薬、カルバマゼピンなど)との相互作用や、pH依存的に吸収される薬剤(抗真菌薬・分子標的薬など)への影響には注意が必要です。
PPIで効果が不十分な場合、夜間症状が残る場合、早く症状を抑えたい場合に特に有用です。H. pylori除菌でも高い除菌率が報告されています。
病態別の使い分け

逆流性食道炎(GERD)では、まずPPIを朝食前に1日1回使用します。症状が強い場合や夜間に胸やけが残る場合は、用量を増やしたり、P-CABへ切り替える選択肢があります。
NSAIDs潰瘍の予防・治療では、リスクの高い患者(高齢者、潰瘍歴、抗血小板薬・抗凝固薬併用など)にはPPIやP-CABを予防的に投与します。漫然と継続せず、定期的に必要性を見直すことが重要です。
H. pylori除菌では、PPIを併用して胃内pHを上げ、抗菌薬の効果を高めます。ボノプラザンを使ったレジメンは高い除菌率が報告されており、一次・二次除菌ともに選択肢になっています。
相互作用と安全性

PPIは主にCYP2C19で代謝されるため、クロピドグレルとの併用に注意が必要です。
ボノプラザンはCYP3Aで代謝されるため、CYP3A阻害薬・誘導薬との相互作用がポイントになります。pH依存吸収薬への影響もPPIより大きく出る可能性があります。
長期使用では、PPI・P-CABともに腸内感染や肺炎のリスク、低Mg血症、鉄・B12吸収障害、骨折リスクなどが議論されています。漫然と長期投与せず、定期的な見直しが重要です。
減量・中止時の注意点

PPIやP-CABを長期間使っていると、急に中止した際に「反跳酸分泌」といって一時的に胃酸分泌が増えることがあります。
これを防ぐために、隔日投与→頓用へ段階的に減量したり、H2ブロッカーや制酸薬を一時的に併用することで安全に中止できます。
まとめ

それぞれの薬剤には「強さ」や「代謝」「飲み方」「相互作用」などに違いがあり、患者さんの状態や併用薬、生活習慣によって最適な薬は変わってきます。
例えば、併用薬が多い高齢者ではラベプラゾール、夜間症状が強いGERDではエソメプラゾールやボノプラザン、除菌療法ではランソプラゾールやボノプラザン、といったように使い分けのイメージを持っておくと実務で役立ちます。


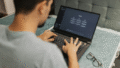
コメント