
近年、医療現場では「薬剤耐性(AMR)」という言葉を耳にする機会が増えています。
AMR(Antimicrobial Resistance:抗微生物薬耐性)は、細菌が抗菌薬に対して効きにくくなる現象で、世界的に深刻な問題になっています。
WHOや厚生労働省も重点的に対策を進めており、薬剤師も日常業務の中で対応が求められています。
この記事では、AMRの基礎知識から、薬剤師が調剤・服薬指導時にできる実践的なポイント、そして活用できる公的資料までをわかりやすく解説します。
なぜ今、薬剤耐性(AMR)が重要なのか

抗菌薬(抗生物質)は、細菌感染症の治療に欠かせない薬です。しかし、使い方を誤ると耐性菌が生まれ、薬が効かなくなるという大きなリスクがあります。
耐性菌は一度広がると抑えるのが難しく、通常の感染症治療が困難になるだけでなく、医療費の増大・治療期間の延長・死亡率の上昇など、多方面に悪影響を及ぼします。
世界ではすでに、薬剤耐性菌による感染症で年間数十万人が死亡しており、2050年には年間1000万人が死亡するとの試算もあります。日本でも耐性菌の拡大や抗菌薬の不適切な使用が課題となっています。
このような背景から、薬剤師が日常の調剤・服薬指導の中でAMR対策を実践することが重要になっているのです。
薬剤耐性(AMR)の基礎知識|仕組みと現状を理解しよう

AMRとは?耐性菌が生まれる仕組み
AMRとは、細菌が抗菌薬に対して「効かない」あるいは「効きにくい」状態になることです。
これは、細菌が持つ遺伝子の突然変異や、他の菌から耐性遺伝子を受け取ることで起こります。こうした菌を「耐性菌」と呼びます。
有名な耐性菌には以下のようなものがあります。
- MRSA:メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
- ESBL産生菌:セフェム系抗菌薬に耐性を持つ腸内細菌
- カルバペネム耐性菌:最終手段の抗菌薬が効かない菌
これらは医療現場での感染症治療を難しくし、重篤な結果を招くことがあります。
日本の現状と国の対策
日本では2016年に「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」が策定され、2023年には新しいフェーズに移行しました。
厚生労働省は、抗菌薬の使用量削減と耐性菌の発生抑制を目標に掲げ、医療機関・薬局・市民が一体となって対策を進めています。
抗菌薬の適正使用(Antimicrobial Stewardship)の基本

AMR対策の中心となるのが、抗菌薬の適正使用(Antimicrobial Stewardship:ASP)です。
薬剤師は、調剤・服薬指導・疑義照会など日常業務の中でこの取り組みに大きく貢献できます。
適正使用の3本柱
- 本当に必要なときに使う(不要な処方を避ける)
- 適切な薬剤を選ぶ(原因菌・重症度・既往に応じて選択)
- 適切な量と期間で使う(漫然と長期投与しない)
これらが守られないと、耐性菌が増えるリスクが高まります。
よくある不適正使用の例
- 風邪やインフルエンザなど、ウイルス感染症への抗菌薬処方
- 医師の「念のため」処方による広域抗菌薬の投与
- 患者による自己中断・飲み残し
- 長期投与や重複投与
薬剤師がこうした処方や服薬状況に気づき、適切に対応・説明することが重要です。
調剤時に薬剤師ができるAMR対策

処方内容のチェック
- 投与量・投与間隔・投与期間がガイドラインに沿っているか
- 重複処方がないか
- 腎機能や年齢による投与量の調整が必要ないか
- 抗菌薬の種類が適切か(狭域薬で対応可能か)
不明な点があれば医師へ疑義照会し、必要に応じて処方変更を提案することもあります。
併用薬・相互作用の確認
PPI(プロトンポンプ阻害薬)や下剤、整腸剤などとの併用によって、抗菌薬の吸収・効果が変わる場合もあります。
併用状況を確認し、必要に応じて服薬時間や内容を調整します。
患者への説明・情報提供
- 「症状が治まっても、指示された日数は飲み切ってください」
- 「途中でやめると菌が残って、薬が効かない菌が増える原因になります」
- 「風邪やウイルス感染には抗生物質は効きません」
こうした基本的な服薬遵守(アドヒアランス)指導がAMR対策の第一歩です。
服薬指導で伝えたいAMRの基本メッセージ

よくある患者さんの質問と対応例
- Q:「熱があるから抗生物質が欲しい」
→ A:「抗生物質は細菌に効く薬です。風邪などウイルスの感染では効かないことが多く、必要なときだけ使うことが大切です。」 - Q:「症状が良くなったから薬は途中でやめてもいい?」
→ A:「途中でやめると、菌が残って薬が効かなくなる原因になるので、最後まで飲み切ることが大切です。」 - Q:「飲み忘れたらどうすればいい?」
→ A:「気づいたときにすぐ飲んでください。ただし、2回分をまとめて飲まないようにしましょう。」
わかりやすく伝える工夫
「耐性」という言葉は難しく感じる患者さんも多いため、
「薬が効かない菌が増える」「菌が薬に強くなる」といったやさしい言い回しが有効です。
厚労省や国立感染症研究所が提供するリーフレットやイラスト素材を活用するのもおすすめです。
薬局・病院で活用できる公的資料・情報源

日本の公的資料
- 厚生労働省:薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120172.html - 国立感染症研究所(NIID):JANIS(耐性菌サーベイランス)
→ https://janis.mhlw.go.jp/ - 抗菌薬適正使用の手引き/患者向けリーフレット
→https://amr-onehealth-platform.jihs.go.jp/home
まとめ|薬剤師はAMR対策の最前線に立つ存在

AMRは医師だけでなく、薬剤師が日々の調剤・服薬指導で関わることで大きな効果を発揮できる分野です。
まずは以下の3つから始めてみましょう。
- 処方内容のチェックと疑義照会
- 服薬遵守の基本的な説明
- 公的資料の活用による啓発
一人ひとりの説明・対応の積み重ねが、耐性菌拡大の防止につながります。
薬局のカウンターこそ、AMR対策の「最前線」です。

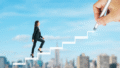

コメント