―なぜアモキシシリンが第一選択なのか、代替薬の選び方まで解説―
1. 溶連菌(A 群β溶血性連鎖球菌)感染症とは

溶連菌は、主にのどに感染して「強いのどの痛み」「高熱」「発疹」を引き起こす細菌です。小児に多い病気と思われがちですが、実は大人にも感染します。
特に「溶連菌咽頭炎」や「猩紅熱」といった病気の原因菌であり、放置するとリウマチ熱(心臓弁膜症の原因)や急性糸球体腎炎(腎臓障害)など、重い合併症を起こすことがあります。これらの合併症は感染から数週間後に発症することがあり、適切な抗菌薬治療で予防できるため、早期診断と治療がとても重要です。
最近では、のどの痛みだけでなく「手足の強い痛み」や「皮膚の壊死」を伴う劇症型溶連菌感染症(STSS)の報告も増え、ニュースになることもあります。このため、溶連菌感染症の治療に対する注目度が高まっています。
2. なぜ抗生剤が必要なのか

「のどの風邪は自然に治ることも多いのに、溶連菌ではなぜ抗生剤を使うの?」と疑問に思う人もいるでしょう。理由は次の3つです。
- 症状の改善が早まる
抗菌薬を使うことで、のどの痛みや発熱の期間が1~2日短縮されます。 - 重い合併症を防ぐ
抗菌薬を適切に使うと、リウマチ熱の発症を70~80%減らすことができます。 - 周囲への感染を防ぐ
抗菌薬を始めてから24時間経過すると、人にうつすリスクが大幅に下がります。
このように、症状の改善だけでなく「合併症予防」と「家族や友人にうつさないため」でも、抗菌薬治療は重要なのです。
3. 抗菌薬を使う前に診断を確認

最近の医療現場では、必要のない抗生剤を使わないという考え方が広がっています。ウイルスによる風邪と区別するため、まずは「溶連菌かどうか」を判断する検査が行われます。
- Centor/McIsaacスコア
のどの発赤、膿、発熱など5項目で点数化し、溶連菌の可能性を予測します。 - 迅速抗原検査
綿棒でのどの奥をこすり、10分ほどで結果が出る検査。陽性ならほぼ確定です。
検査が陰性なら抗菌薬は不要です。これにより、耐性菌を増やさないようにすることができます。
4. 第一選択はアモキシシリン

溶連菌にはペニシリン系の抗菌薬が最も効果的で、その中でもアモキシシリンが標準薬です。世界中で長年使われ、耐性菌もほとんど出ていないため、非常に信頼性があります。
一般的な用量例(10日間):
- 成人:500mgを1日3回
- 小児:25~50mg/kgを2~3回に分けて
なぜ10日間?
細菌を完全に死滅させるためには、症状が良くなっても一定期間飲み続ける必要があります。短くすると再発やキャリア化(のどに菌が残る)が起こりやすくなります。
5. 投与期間短縮は可能か?

海外では5~7日間の短縮療法でも10日間と同等の効果があるという研究が出ています。しかし、日本のガイドラインでは再発リスクを考え、10日間が基本とされています。
短縮療法を選ぶ場合は、再受診で経過をチェックするなど、医師と薬剤師の慎重な管理が必要です。
6. ペニシリンアレルギー時の代替薬

「ペニシリンで発疹が出た」「呼吸が苦しくなった」など、アレルギーがある場合は別の薬を使います。
- 軽いアレルギー(発疹程度):セファレキシン(セフェム系)
- 重度アレルギー(呼吸困難など):マクロライド系(クラリスロマイシンなど)
- その他:クリンダマイシン
ただし、マクロライド系は溶連菌の耐性率が30%以上と高く、効果が出ないこともあるため注意が必要です。
7. 抗生剤不足時の対応
2025年にはアモキシシリンが一時的に供給不足となり、現場が混乱しました。こうしたときは、
8. 服薬指導のポイント

- 子どもが飲みにくいときは、フレーバーシロップで味を改善
- 治療開始24時間後は登校・出勤が可能(解熱が条件)
- 「症状が良くなっても途中でやめない」ことを強調
- 家族にうつさないため、タオルや食器を別にする
9. 再発・キャリア対策
一度治ったと思っても、数週間後に再発することがあります。これは菌がのどに残っていたり、家族から再感染したりするためです。こうしたときは再度検査を行い、必要に応じて薬を変更します。
無症状でものどに菌が残っている「キャリア」の場合、基本的に治療は不要ですが、家族に重い病気の人がいる場合は除菌を検討します。
10. 劇症型溶連菌(STSS)は緊急事態
まれに、溶連菌が血液や筋肉に広がり、短時間で命に関わるSTSSを起こすことがあります。手足の激痛、皮膚の赤みや腫れ、急なショック症状があれば、救急搬送が必要です。
治療にはペニシリンG大量投与とクリンダマイシン併用、場合によっては手術が行われます。
11. まとめ

- 溶連菌の治療はアモキシシリン10日間が基本
- 必要なときだけ抗菌薬を使い、検査で診断を確定する
- アレルギーや供給不足時には代替薬を正しく選ぶ
- 服薬を途中でやめないことが合併症や再発を防ぐ鍵
参考URL

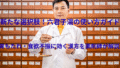

コメント