インターネットでの買い物が当たり前になった今、医薬品もオンラインで購入できるようになってきました。とくに「OTC医薬品(一般用医薬品)」と呼ばれる、医師の処方なしで買える薬については、国の規制が緩和され、オンライン販売がより進められようとしています。
しかしその一方で、「誤った使い方をする人が増えるのでは?」「安全性は大丈夫?」といった不安の声も上がっています。
この記事では、OTC医薬品のオンライン販売規制緩和の内容をわかりやすく解説し、薬剤師が今後果たすべき役割について詳しくご紹介します。
OTC医薬品のオンライン販売規制緩和とは?

OTC医薬品とは?
OTC医薬品は、薬局やドラッグストアで購入できる「一般用医薬品」のことです。風邪薬や頭痛薬、胃腸薬など、日常的な体調不良に対応できる薬が多く含まれています。これらの薬は医師の診察や処方箋がなくても、薬剤師や登録販売者の助言を受けながら購入することができます。
OTC医薬品は、副作用のリスクや使用上の注意事項に応じて、以下の4つの区分に分けられています。
- 要指導医薬品:スイッチ直後で情報提供が特に重要な薬。対面での説明が義務であり、原則としてオンライン販売は不可。
- 第1類医薬品:副作用のリスクが高めで、薬剤師のみが販売できます。購入時には、使用目的や既往歴の確認など、専門的な説明が必要です。
- 第2類医薬品:ややリスクがある薬で、薬剤師または登録販売者が販売できます。使用上の注意点などは比較的簡潔ですが、体質や服用中の薬によっては注意が必要です。
- 第3類医薬品:副作用のリスクが比較的低いとされる薬で、登録販売者が販売できます。うがい薬や整腸剤などが該当します。
OTC医薬品のリスクとは?
OTC医薬品は「処方箋が不要」という手軽さが魅力ですが、それは自己判断による誤使用のリスクとも隣り合わせです。たとえば次のようなリスクが存在します。
- 症状に合わない薬を選んでしまう
- 複数の薬を併用して、有害な相互作用が起こる
- 副作用に気づかず重症化する
- 持病があるのに気づかず、薬が悪化の引き金になる
とくに高齢者や持病のある人、妊娠中の女性などは注意が必要です。また、子どもへの使用についても、安全性の面から専門的な判断が欠かせません。
どのような規制緩和が行われているの?
これまで、第1類医薬品や要指導医薬品など、リスクの高い薬は「対面販売」が基本でした。特に要指導医薬品については、薬剤師が直接対面で情報提供しなければならず、オンライン販売は原則禁止されています。
しかし、平成26年から規制緩和により、第2類、第3類医薬品以外にも第1類医薬品についても、一定の条件を満たせばオンラインで販売できるようになりました。具体的には、以下のような取り組みが進められています。
- 薬剤師によるリモートでの服薬指導が認められるように
- 購入前の確認事項(症状・既往歴など)のオンラインチェックを義務化
- 販売履歴や相談内容の記録・管理に特定のITシステムを活用
こうした制度改正によって、利便性を高めつつ、安全性も確保することが狙いとされています。しかし、実際に安全性がどこまで担保されるのかは、制度の運用次第でもあり、今後も課題は残っています。
オンライン販売と対面販売の違い

情報提供の深さと安全性の違い
薬局で薬を買うとき、薬剤師が症状や既往歴を聞いて、最適な薬を提案してくれます。対面なら、表情や口調からも状態を判断できます。
一方、オンラインではどうしても画面越しのやりとりになり、微妙なニュアンスや体調の変化を読み取りにくいという課題があります。
販売時の確認義務とトラブルのリスク
オンラインでは、購入者が自己申告した情報に基づいて販売が行われます。そのため、以下のようなリスクが懸念されます。
- 症状に合わない薬の購入
- 同じ成分の薬を重複して使用する
- 副作用や相互作用の見逃し
特に、高齢者やインターネットに不慣れな人にとっては、間違った使い方をしてしまう危険が高くなります。
薬剤師が果たすべき新たな役割

オンラインでの適正使用支援
薬剤師には、薬の適正使用をサポートする使命があります。オンライン販売が増える中でも、チャットやビデオ通話、メールなどの手段を使って、的確な情報提供やアドバイスを行うことが求められます。
これまでの「対面重視」の働き方から、デジタルを活用した支援へとシフトする必要があります。
服薬フォローアップの重要性
薬を売ったあとの「フォローアップ」も薬剤師の大切な仕事です。特に、長期的に薬を使用する場合や副作用が出やすい薬では、継続的な健康観察が必要です。
今後は、電子お薬手帳やアプリを使った健康管理支援など、ICTを活用したフォローアップの仕組みが重要になります。
薬剤師の倫理観とプロ意識の再確認
オンライン販売の拡大により、OTC医薬品がこれまで以上に“手軽に”購入できるようになる中で、薬剤師にはこれまで以上に倫理観とプロ意識が求められます。
「売れればいい」「便利だからいい」といった短期的な利益を追い求める姿勢では、患者さんの健康や命を守ることはできません。たとえば、売上重視で十分な情報提供を省略したり、リスクの高い医薬品を安易に勧めたりすれば、それは専門職としての責任を放棄することにもつながります。
薬剤師は、医薬品の専門家として、次のような行動が求められます。
- 患者の背景を理解しようとする姿勢
→年齢、持病、他の服薬状況、生活習慣などに配慮したアドバイスを行う - 十分な情報提供と確認を行うこと
→特にオンラインでは一方通行になりやすいため、理解度を確認しながら丁寧な説明を心がける - 必要であれば販売を断る勇気を持つこと
→使用が不適切と判断される場合、販売しないという選択ができるのは薬剤師だからこそ
また、オンライン化が進むことで、システムに依存する場面も増えます。しかし、機械的なチェックだけでは拾えない“違和感”や“危険な兆候”を見抜けるのは人間の目だけです。そうした感覚は、現場経験や職業倫理を持った薬剤師だからこそ発揮できる力です。
OTCオンライン販売時代に薬局が生き残るために

OTC医薬品のオンライン販売が進む中で、利用者は「近くの薬局で薬を買う」だけでなく、「自宅にいながら薬を注文・相談する」という選択肢を持つようになりました。
このような変化の中で、地域の薬局が生き残るためには、ただ薬を販売するだけの場から“選ばれる薬局”へと変化する必要があります。
「相談できる場」としての薬局の価値を高めること
オンライン販売では、便利さは得られる一方で、個別の相談対応や信頼感といった対面ならではの価値は得にくい傾向があります。薬局が持つ強みのひとつは、「直接話して安心できる」「その場で状態を見てアドバイスをもらえる」といった“人の温かさ”です。
したがって、薬局は「薬を買う場所」から、「気軽に健康のことを相談できる場所」へと価値を再定義し、来局の動機を増やす工夫が求められます。
LINEや専用アプリでの相談受付など、オンライン対応を整えること
いくら対面の価値が高くても、忙しい現代人にとってオンラインで気軽に相談できる仕組みも同時に重要です。例えば、以下のような取り組みが効果的です。
- LINEを使った健康・薬の無料相談サービスの導入
- 処方箋送信や事前相談ができるアプリの導入
- オンラインでの服薬フォローや副作用チェックの実施
これにより、「この薬局は便利で、しかも相談できて安心」と利用者に感じてもらうことができます。
まとめ|オンライン化の波の中で薬剤師が担うべき責任

OTC医薬品のオンライン販売は、利用者の利便性を高める一方で、誤用や健康被害のリスクも伴います。
だからこそ、薬剤師にはこれまで以上に知識・判断力・責任感が求められます。単に薬を「売る」のではなく、安心して薬を使ってもらうための支援者として、デジタル時代にふさわしい新しい形の関わり方を模索していくことが大切です。

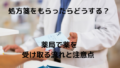

コメント