近年、SNSなどで「風邪薬を飲むと落ち着く」「頭痛薬が手放せない」といった投稿を見かけることが増えていませんか?
実は、こうした背景には市販薬の乱用・依存という、見えにくい社会問題があります。
今回は、なぜ市販薬の乱用が問題なのか、どのようなリスクがあるのか、そして私たち薬剤師にできる予防策について、現場の視点でわかりやすく解説します。
市販薬の乱用・依存とは?

まず、「乱用」や「依存」という言葉の意味から整理しましょう。
市販薬の乱用とは、本来の目的や用法・用量を超えて薬を使用すること。
たとえば、「風邪薬を眠るために毎日飲む」「咳止めを気分を良くするために大量に飲む」といった行為が該当します。
さらに、その使用がやめられなくなってしまう状態が依存です。
身体的・精神的に薬に頼るようになり、やめると不安や不調を感じるようになります。
一見、安全そうに思える市販薬ですが、使い方を間違えると深刻な健康リスクにつながるので注意が必要です。
どうして市販薬の乱用が問題なの?

市販薬は医師の処方がなくても買える手軽さがあります。
しかし、乱用を続けると次のような問題が起こります。
- 身体への影響:肝臓や腎臓へのダメージ、中毒症状、吐き気、眠気、意識障害など
- 精神的な依存:薬がないと不安になる、気分が落ち着かない
- 日常生活への影響:学校や仕事に行けなくなる、人間関係のトラブル
特に10代〜20代の若年層は、ストレスや孤独、SNSなどの影響から薬に手を伸ばすケースも多く、社会的な問題になりつつあります。
よく乱用される市販薬とは?

具体的に、どんな市販薬が乱用されやすいのでしょうか?
以下は注意が必要な代表的な例です。
1. 風邪薬(抗ヒスタミン成分)
眠くなる成分を利用して「リラックスしたい」「寝つきをよくしたい」という目的で使われがちです。
2. 咳止め(デキストロメトルファンなど)
多幸感を求めて大量に摂取されることがあります。特にアメリカでは問題が深刻化しています。
3. 頭痛薬・鎮痛薬
連用により「薬物乱用頭痛」が起こることもありますが、それに気づかずさらに薬を増やしてしまうケースも。
4. 下剤・便秘薬
摂食障害との関係が指摘されています。ダイエット目的での乱用もあります。
これらはすべて、ドラッグストアで誰でも簡単に買えてしまうのが問題の難しさでもあります。
なぜ市販薬を乱用してしまうのか?

乱用の背景には、さまざまな心理的・社会的な要因があります。
- 人間関係や家庭環境のストレス
- 学校や職場での孤独感
- 「眠れない」「落ち着かない」などの精神的な不調
- 医療機関に相談しづらい、受診のハードルが高い
- SNSでの誤情報や口コミ
- 「市販薬だから安全」と思い込んでしまう誤解
このような環境が重なると、「誰にもバレずに楽になれる手段」として市販薬に頼ってしまう人が少なくありません。
薬剤師ができる市販薬乱用の予防策

市販薬の乱用や依存は、見えにくいだけに気づかれにくく、深刻化しやすい問題です。
しかし薬剤師は、販売の最前線に立つ立場として、早期にその兆候をキャッチし、予防に繋げる役割を担っています。
ここでは、薬剤師として実践できる具体的な対策を4つご紹介します。
1.販売時の声かけと観察
販売時のちょっとしたやりとりの中に、乱用のサインが隠れていることがあります。
たとえば…
- 同じ薬を数日おきに何度も購入していないか?
- 薬の説明を聞くのを嫌がったり、「とにかくその薬がほしい」と急ぐ様子はないか?
- 顔色が悪い、目を合わせない、挙動不審など、不自然な様子がないか?
これらの行動は、薬に依存しつつあるサインかもしれません。
また、会話の中で「どんな目的で使っているのか」「どれくらい前から使っているのか」などをさりげなく質問することで、過剰使用の傾向に気づけることもあります。
薬剤師の観察力と声かけは、乱用の予防において非常に重要なファーストステップです。
2. 正しい情報提供
市販薬は「自由に買える」反面、自己判断で間違った使い方をしてしまいやすいというリスクもあります。
そのため、購入時には以下のような具体的で分かりやすい情報提供が大切です。
- 薬は決められた用法・用量を守ることが安全に使う前提であること
- 「眠くなる成分が入っているから寝る前に飲んでいる」という使い方は、本来の目的外であり危険であること
- 「長期間の使用」や「量を増やすこと」によって、依存や副作用のリスクが高まること
ただ注意をするのではなく、相手の立場に寄り添いながら、優しく・的確に伝えることが信頼関係の構築にもつながります。
3. 薬歴や販売記録の活用
店舗によっては、OTC(一般用医薬品)の販売記録を残すことができるシステムを導入しているところもあります。
この記録を活用することで、同じ成分の薬を定期的に購入していないか、複数店舗で同じ薬を買っている可能性がないかといった傾向を把握することができます。
また、セルフメディケーションで対応できる範囲を超えていると感じた場合には、無理に販売を続けるのではなく、医療機関への受診をやさしく提案することも必要です。
「病院に行くのは大げさだ」と思っている方に対しては、「今のうちにしっかり診てもらっておいたほうが安心ですよ」といった前向きな声かけが効果的です。
4. 必要に応じた多職種連携
もし、明らかに依存や乱用が疑われるケースに遭遇した場合、薬剤師ひとりで抱え込まずに、必要に応じて多職種と連携することが大切です。
具体的には、
- 医師(かかりつけ医や精神科医)
- 地域の保健師や保健所
- 家族(必要に応じて)
などと連携し、適切な医療支援へとつなげることが、本人の健康を守る第一歩になります。
ただし、本人の同意やプライバシーに配慮しながら、無理のない範囲で関係機関とつながる配慮が必要です。
薬剤師の情報発信も力になる

市販薬の乱用や依存を防ぐためには、薬を販売する現場だけでなく、正しい情報を社会に広めていくことも大切です。
薬剤師が積極的に情報発信を行うことで、市販薬に関する誤解や危険な使い方を防ぎ、正しい知識を広める力になります。
以下に、具体的な発信方法や意識すべきポイントをご紹介します。
1.店頭での注意喚起
薬局やドラッグストアでは、店頭ポップや掲示物を使って、来店者にわかりやすく注意を促すことができます。
- 「風邪薬の眠気成分を睡眠目的で使うのは危険です」
- 「咳止めの長期使用は、体への負担につながることがあります」
- 「薬は正しく使ってこそ効果があります」
このような一言メッセージを、見やすい場所に掲示することで、自然に意識してもらうことができます。
視覚的に伝えることで、言葉で伝えるよりも気軽に、広い層にアプローチできる点が魅力です。
2.誤情報に流されないための“信頼できる存在”に
ネットには、市販薬に関する不正確な情報や危険な使い方の体験談があふれています。
たとえば「○○の薬を飲んだらスッキリした」「眠れないときは××がいい」など、実際にはリスクのある使い方が広まっていることも少なくありません。
そんなとき、薬剤師が正しい知識を伝えることで、「この情報は信頼できる」と思ってもらえる存在になることができます。
薬に関する専門家としての立場を活かし、日常の中で気軽に読める形で発信することが、結果的に乱用予防につながるのです。
3.情報発信も「地域医療の一部」
薬剤師の情報発信は、単なる広報活動ではありません。
それは、地域や社会の人々の健康を守る「予防医療の一環」です。
「正しい情報を、正しいタイミングで、必要な人に届ける」
この積み重ねが、未来の乱用・依存を減らし、薬を安心して使える社会づくりに貢献していきます。
まとめ:市販薬乱用は、身近にある社会問題

市販薬の乱用や依存は、「他人ごと」ではありません。
気づきにくく、でも深刻な影響をもたらす可能性のある問題です。
薬剤師として、日常の販売や接客の中で小さな違和感に気づくこと、正しい知識を伝えることが、本人の健康を守る第一歩になります。
一人でも多くの人が「薬を正しく使う」ことができるよう、私たちの専門性が求められています。
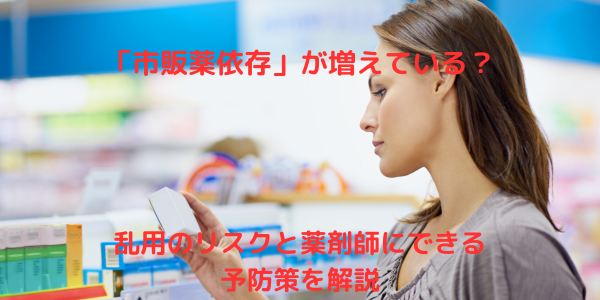


コメント