吸入薬は種類が多く、機序も似ているように見えるため、薬剤師でも「この患者に本当に合っているのか」を判断しにくい領域です。特に ICS(吸入ステロイド)、LABA(長時間作用型β2刺激薬)、LAMA(長時間作用型抗コリン薬)は、名前こそ似ていますが、病態のどこを治療する薬なのかが大きく異なります。その違いを理解すると、喘息・COPD・境界領域(ACO)の吸入治療が驚くほど読みやすくなります。
この記事では、吸入 ICS/LABA/LAMA の違いと “本当に効く使い分け” を、最新エビデンスと実務の観点から包括的にまとめます。
- 1. まず結論:使い分けの軸は「病態」「好酸球」「増悪リスク」
- 2. ICS/LABA/LAMA は「どこに効く薬なのか」が根本の違い
- 3. 喘息:ICS/LABA が基本形。ICS を抜く選択肢はほぼない
- 4. COPD:LAMA/LABA が軸。ICS は必要な人だけに使う
- 5. 境界領域(ACO):喘息と COPD が混ざる “厄介ゾーン”
- 6. 三剤併用(ICS/LABA/LAMA)は“誰にでも”ではない
- 7. 効果を左右する“デバイス選択”:薬より大事なこと
- 8. ケースで理解する「本当に効く使い分け」
- 9. まとめ:病態・好酸球・デバイスの三本柱で最適解は変わる
- 参考URL
- 吸入薬の知識を活かすためには職場環境が重要
1. まず結論:使い分けの軸は「病態」「好酸球」「増悪リスク」

吸入薬の使い分けで迷いやすいのは、見た目が似ているためです。しかし、判断軸を整理すると非常にシンプルになります。
- 喘息では ICS が必須
喘息は好酸球主体の炎症が根本にあるため、ICS 抜きではコントロールは難しい。 - COPD では LAMA/LABA が基本
閉塞主体の病態なので、気道を広げる LABA/LAMA を中心に組み立てるのが最適。 - ICS を追加するかは、好酸球と増悪回数で決める
好酸球 300 以上、増悪を年 2 回以上繰り返す場合は ICS のメリットが大きい。
この 3 つの軸が理解できれば、処方意図の大部分は読み解けます。
2. ICS/LABA/LAMA は「どこに効く薬なのか」が根本の違い

吸入薬の分類は、そのまま「病態のどこをターゲットにしているか」を示しています。
● ICS(吸入ステロイド)
気道の好酸球炎症を抑える薬で、喘息の根本治療。
症状改善だけでなく、増悪(急性悪化)を大きく減らす効果があります。
COPD では炎症の割合が少ないため、全員に効くわけではありません。
● LABA(長時間作用型β2刺激薬)
気道平滑筋を緩め、空気の通り道を広げる薬です。
喘息でも COPD でも使用されますが、喘息では「ICS との併用」が原則です。
● LAMA(長時間作用型抗コリン薬)
迷走神経性の気道収縮を解除し、閉塞を改善する薬です。
COPD の第一選択になりやすく、喘息でも閉塞優位の症例では追加の選択肢になります。
このように、ICS は炎症、LABA/LAMA は閉塞という“得意分野”の違いを理解すると、各診療領域での薬剤選択が自然に見えてきます。
3. 喘息:ICS/LABA が基本形。ICS を抜く選択肢はほぼない

喘息は「炎症中心の病態」であり、ICS を使わずに LABA だけで治療することは原則として推奨されていません。炎症を抑えずに気道を広げるだけでは、増悪を繰り返すリスクが高まります。
したがって、世界的な標準治療は
・ICS/LABA 併用
です。
症状が残る場合や閉塞が強い症例では
・ICS/LABA + LAMA
という三剤併用が検討されます。これは「喘息の閉塞成分」を改善する目的で、効果を実感するケースが多く見られます。
ICS の減量は慎重に判断する
増悪が長期間みられない、日中・夜間症状が安定しているなど、条件が揃った場合は ICS の減量が可能ですが、急ぎすぎると再燃しやすいため注意が必要です。
4. COPD:LAMA/LABA が軸。ICS は必要な人だけに使う

COPD は閉塞主体の病態です。したがって、気道を広げる作用を持つ LAMA/LABA の二剤併用がもっとも理にかなった治療となります。
ICS は COPD の全員に効くわけではなく、むしろ肺炎リスクが上昇することが知られています。そのため ICS の追加は慎重であり、次の条件が重要になります。
● ICS が有効になりやすい人
- 好酸球数が 300 以上
- 増悪を年 2 回以上繰り返している
- 過去に ICS 使用で明らかな改善がみられた
● ICS で注意が必要な人
・好酸球が低い
・過去に肺炎を繰り返している
・高齢で嚥下・口腔ケアに不安がある
COPD では ICS を漫然と使うのではなく「必要な人を選ぶ」ことが安全性の確保につながります。
5. 境界領域(ACO):喘息と COPD が混ざる “厄介ゾーン”

ACO(Asthma-COPD Overlap)は、喘息と COPD の特徴を併せ持つ患者です。
喫煙歴がありながら好酸球が高く、ICS で改善する症例が典型です。
ACO のポイントは
・ICS を抜くと悪化しやすい
・閉塞が強い場合は LAMA 追加が有効
という“二面性”を理解することです。
薬剤師としては、
・若い頃からの喘鳴歴
・アレルギー疾患の併存
・好酸球の高値
・ステロイドで反応が良い
といった情報を拾うと、ACO の存在を早期に察知できます。
6. 三剤併用(ICS/LABA/LAMA)は“誰にでも”ではない

三剤併用は「全部入りだから強い」という誤解が生まれやすいですが、実際には適応が明確であり、有効な患者群は限られています。
三剤が特に有効なケース
- 気道閉塞が中等度以上
- 増悪を繰り返している
- 好酸球が高い
- ICS/LABA だけでは症状や閉塞が残る
特に COPD や ACO での増悪抑制効果は大きく、救急受診や入院を減らす可能性があります。
しかし、三剤併用の効果は「吸入手技」が正しく行われることが前提です。どれだけ薬理的に適切でも、デバイスが合わなければ治療効果は得られません。
7. 効果を左右する“デバイス選択”:薬より大事なこと

吸入薬は内服薬とは違い、正しく吸い込めなければ薬効がほとんど得られません。特に高齢者では、デバイスの選択が薬効の 8 割を左右するといっても過言ではありません。
● DPI(ドライパウダー)
強い吸気が必要。吸気流速が弱い患者では薬が肺に届かない。
● pMDI(エアゾール)
押しながら吸うという動作が難しい。タイミングのズレで効果が低下。
● SMI(ソフトミスト)
ゆっくりミスト状に噴霧されるため、吸いやすい。高齢者に向いている。
薬剤師としては、
・吸気力の確認
・息止めの可否
・押し吸いの理解
といったチェックを 1 分行うだけで治療効果が劇的に変わります。
8. ケースで理解する「本当に効く使い分け」

ここでは、現場でよく遭遇する患者像をもとに解説します。
ケース1:喘息で閉塞が軽度
ICS/LABA が基本。症状が残る場合は LAMA 追加を検討。
ケース2:喫煙歴が長く、閉塞強いが好酸球低値
LAMA/LABA を優先。ICS は慎重に使用。
ケース3:増悪を繰り返し、好酸球も高い
三剤併用が強く推奨されるケース。
ケース4:高齢で吸気流速が弱い
DPI は不適。SMI や pMDI が適している。
ケース5:吸入のタイミングが理解しにくい
ゆっくり吸える SMI が最優先候補。
ケースごとに「なぜその選択になるのか」を説明できれば、服薬指導は格段に説得力を持ちます。
9. まとめ:病態・好酸球・デバイスの三本柱で最適解は変わる

吸入 ICS/LABA/LAMA の使い分けは、単なる薬効の強さ比較ではありません。
病態の中心がどこにあるか、炎症が強いか、閉塞が中心か、好酸球はどうか、増悪リスクはどうか。そして、その人がデバイスを使いこなせるか。
この三本柱を整理するだけで、吸入薬の選択は驚くほど明確になります。
・炎症→ ICS
・閉塞→ LABA/LAMA
・混在→ 三剤
・デバイス適合性→ 効果を左右する最大の要因
薬剤師がこれらを理解すると、処方意図を読み解けるだけでなく、患者に合わせた吸入指導ができ、治療効果を最大化できます。
今日の服薬指導から実践できる内容をぜひ取り入れてみてください。
参考URL
Japanese Society of Allergology “Adult Asthma 2021
Inhaled-combination therapies (ICS/LABA/LAMA) in COPD
ぜん息の薬,独立行政法人環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/medicine.html
吸入薬の知識を活かすためには職場環境が重要
吸入薬の使い分けは、薬剤師としての知識と経験がもっとも発揮される領域です。患者さんの症状が改善していく様子を実感できる一方で、忙しい職場では一人ひとりに丁寧な吸入指導を行う時間が取れず、ジレンマを抱えることもあります。
もし今の職場で
・患者さんにしっかり関わる余裕がない
・呼吸器や在宅など専門領域をもっと伸ばしたい
・働き方の選択肢を増やしたい
と感じることがあるなら、一度「今より良い環境」を知っておくことは無駄になりません。
ファルマスタッフ は調剤薬局に強く、在宅導入店や教育体制が整った薬局の求人も扱っており、呼吸器領域を深めたい薬剤師にも選択肢が広いのが特徴です。登録したからといって転職を急かされることもなく、情報収集として利用している薬剤師も多くいます。
働き方に少しでも悩みがあるなら、まずは“今の自分の市場価値”を知るところから始めてみても良いかもしれません。


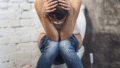
コメント