はじめに

フィブラート系薬(フィブラートと略されることもあります)は、血液中の中性脂肪(TG:トリグリセリド)を下げるのが得意な薬です。薬剤師が現場でよく出会うのは、健診や外来で「TGが高い」と言われた患者さんに処方されるケース。特にTGが非常に高い場合(例:500 mg/dL以上)では、急性膵炎を予防するために早急に下げる必要があるため、フィブラートが第一選択になることがあります。
一方で、「心筋梗塞や脳梗塞を減らせるか?」という心血管アウトカムについては、大規模試験で全体的には効果が中立とされており、必ずしも“誰にでもメリットがある”薬ではありません。薬剤師は、TGの値・合併症・腎機能・併用薬などを考えながら、適応やリスクを見極める必要があります。
フィブラートの基本作用

どうやって中性脂肪を下げるのか?
フィブラートはPPARα(ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体α)という体内のスイッチをオンにします。これにより、肝臓や筋肉で脂肪酸を燃やす力が高まり、さらに血中でTGを分解する酵素(リポ蛋白リパーゼ)が働きやすくなります。結果として、
- TGが20〜50%下がる
- HDL(善玉コレステロール)が少し上がる
といった効果が得られます。ただし、LDLコレステロールにはっきりとした改善効果はなく、むしろ増減が患者によってばらつく点には注意が必要です。
どんな場面で使うのか?

膵炎予防が最優先
TGが500 mg/dLを超えると、膵炎のリスクが一気に高くなります。この場合、まず「TGを500未満に下げること」が最優先であり、そのためにフィブラートが処方されます。膵炎は命に関わる合併症なので、薬の使いどころが非常に明確です。
TGが軽〜中等度に高いとき
スタチンを使ってもLDLがコントロールされているのにTGが200〜499 mg/dLと高いまま残っている患者もいます。この場合、動脈硬化をさらに抑える目的でフィブラート追加が検討されます。ただし、この場合の効果は「心血管リスク全体を減らす」という意味では限定的であり、特に“TGが高くてHDLが低い”タイプの患者で効果が期待できる可能性があると報告されています。
参考URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jat/31/6/31_GL2022/_html/-char/ja
日本でよく使われる薬剤の特徴

- フェノフィブラート:腎機能によって用量調整が必要。スタチン併用が必要ならフェノフィブラートを優先。ジェムフィブロジルは原則回避。血清クレアチニンが一時的に上がることがあるが、多くは可逆的。
- ベザフィブラート:歴史が長い薬。尿酸を下げる作用がある報告もあるが、スタチンとの併用では筋障害のリスクに注意。
- クリノフィブラート:使われる頻度は減っているが、胆石リスクなどクラス全体の注意点は共通。
- ペマフィブラート:副作用が少ないと期待された新薬だが、大規模試験では心血管リスク低下は示せなかった。腎機能への負担が少ないとの報告あり。
- ジェムフィブロジル:スタチンとの相互作用が強く、筋障害のリスクが高いため現在はほとんど使われない。
安全性とモニタリング

よくある副作用
- 肝機能障害(定期的にAST/ALTチェック)
- 腎機能への影響(血清Crが上がることがある)
- 筋障害・横紋筋融解(特にスタチン併用時)
- 胆石(胆汁の性質が変わるため)
- 光線過敏(日光で皮疹が出ることがある)
検査スケジュール
- 開始前:肝機能・腎機能・脂質値
- 開始後:脂質/TGは開始後4–8週で再評価し、その後も適宜フォロー。肝機能(AST/ALT等)は国内ラベルで “開始3か月までは毎月、その後は3か月ごと”が目安。腎機能も定期的に確認。
- 筋肉症状が出たとき:すぐCKを測定
相互作用に注意すべき薬

- スタチン:フェノフィブラートなら比較的安全に併用できるが、ジェムフィブロジルはNG。
- ワルファリン:作用を強めて出血しやすくなるため、INRをしっかりチェック。
- シクロスポリン・タクロリムス:腎機能悪化のリスク。併用は避けるか慎重に。
腎機能による使い分け

- eGFR ≥60:通常量で使用可能
- eGFR 30〜59:低用量から慎重に開始
- eGFR <30:多くの製剤で禁忌。透析中も避ける
高齢者では特に腎機能を頻回にチェックする必要があります。
服薬指導のポイント

患者さんに説明するときは「なぜこの薬を飲むのか」を分かりやすく伝えることが大切です。
- 「中性脂肪が高いと膵炎を起こす危険があるので、まず数値を下げましょう」
- 「筋肉痛やだるさが出たらすぐ教えてください」
- 「胆石の症状(右のあばらの下の痛みや吐き気)が出たら受診を」
- 「日焼けで皮疹が出ることがあるので、長時間の直射日光は避けましょう」
- 「検査で効果と副作用をチェックしますので、次回採血の日を守ってください」
まとめ

フィブラートは「膵炎予防のためにTGを下げる」薬としての位置づけが明確です。心血管イベント抑制の効果は限定的で、使う患者を選ぶ必要があります。腎機能や併用薬を確認し、検査と患者教育を徹底することで、安全かつ有効に活用できます。

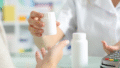

コメント