作用の違い・副作用・臨床現場での注意点をわかりやすく解説
1. はじめに

「利尿剤」と聞くと、トイレが近くなる薬、むくみを取る薬というイメージがあるかもしれません。
その中でも「カリウム保持性利尿剤」は、体の中のカリウムを排泄しにくくする特徴を持ち、他の利尿剤とは少し違った役割を持つ薬です。
通常の利尿剤(ループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬)は、ナトリウムと一緒にカリウムも排泄してしまうため、低カリウム血症の副作用が心配されます。
一方で、カリウム保持性利尿剤はカリウムを体に残す作用があるため、そういったリスクを軽減できます。
この記事では、カリウム保持性利尿剤の種類ごとの違いや特徴、副作用への対応などを解説します。
2. カリウム保持性利尿剤とは?—2つのタイプとその仕組み
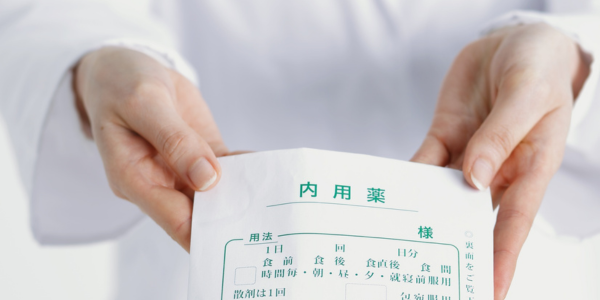
カリウム保持性利尿剤は、次の2つのタイプに分けられます。
| 分類 | 主な薬剤 | 作用点 | 特徴 |
| ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA) | スピロノラクトン、エプレレノン、フィネレノン | 腎臓の集合管でアルドステロンを阻害 | 心不全や高血圧の予後改善に使われることが多い |
| 上皮性ナトリウムチャネル遮断薬(ENaC阻害薬) | トリアムテレン、アミロライド | 遠位尿細管のナトリウムチャネルをブロック | 低カリウム血症の補助目的で用いられることが多い |
▷ なぜカリウムを保持できるのか?——腎臓でのイオン交換の仕組みから理解する
カリウム保持性利尿剤が「カリウムを体内に保持できる理由」は、腎臓における“ナトリウムとカリウムの交換”という基本的な仕組みにあります。
腎臓では、血液から尿を作る過程で「ナトリウムを再吸収し、カリウムを排泄する」という調整が行われています。これは主にネフロンの遠位尿細管から集合管で行われており、ナトリウムが細胞内に入ると、それと引き換えにカリウムが細胞外(尿中)に出ていく仕組みが働いています。
つまり、ナトリウムの再吸収が活発になるほど、カリウムがより多く尿中に出てしまうからです。
❶ ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)
このタイプの薬(スピロノラクトンやエプレレノンなど)は、アルドステロンというホルモンの働きをブロックします。
アルドステロンは本来、腎臓に「ナトリウムを再吸収しなさい。カリウムを出しなさい」と命令するホルモンです。
その命令が遮断されることで、ナトリウム再吸収が抑えられ、結果としてカリウムが体内にとどまりやすくなるのです。
❷ ENaC阻害薬(トリアムテレンやアミロライド)
こちらは、腎臓の集合管にあるENaC(上皮性ナトリウムチャネル)という構造を直接ブロックします。
このチャネルはナトリウムを細胞内に取り込む入り口ですが、それをふさぐことでナトリウムの再吸収ができなくなります。
すると、ナトリウムとカリウムの交換が起きなくなり、カリウムの排泄も抑えられるというわけです。
3. 薬剤別の特徴と使い方

ここでは、代表的な薬剤をそれぞれ詳しく紹介します。作用機序や使い方、副作用、現場での注意点などを丁寧に解説します。
スピロノラクトン
作用機序: アルドステロン受容体をブロックし、ナトリウムの再吸収を抑えることで利尿を促進。
主な適応: 心不全、肝硬変による腹水、高血圧など。
用量の目安: 通常1日25〜100mg。
副作用:
- 高カリウム血症(命に関わることもある)
- 腎機能悪化
- ホルモン関連(女性化乳房、月経不順など)
これは、スピロノラクトンが性ホルモンにも作用するからです。
現場のポイント:
安価でエビデンスも豊富ですが、ホルモン関係の副作用が出やすいため、長期使用時は注意が必要です。高齢男性などではエプレレノンに変更することもあります。
エプレレノン
作用機序: スピロノラクトンと同じくMRAですが、性ホルモン受容体への作用が弱いため副作用が少なめ。
主な適応: 心不全(特に心筋梗塞後)、高血圧。
用量の目安: 25〜50mg/日。
副作用:
- 高カリウム血症
- 腎機能悪化
- 代謝酵素(CYP3A4)で分解されるため、薬の飲み合わせに注意が必要
現場のポイント:
スピロノラクトンで副作用が出た場合や、副作用を避けたい患者にとって良い選択肢です。
フィネレノン
作用機序: 新しいタイプのMRA。より選択的かつ抗炎症・抗線維化作用が強い。
主な適応: 2型糖尿病を伴う慢性腎臓病(CKD)の進行抑制。
用量の目安: 20mg/日。
副作用: 高カリウム血症(頻度は少なめ)、腎機能悪化。
現場のポイント:
利尿目的ではなく、心臓・腎臓の保護目的で使用されます。食事や他の薬とのバランスも大切になります。
トリアムテレン
作用機序: ENaCというナトリウムチャネルをブロックしてナトリウムの再吸収を抑える。
主な適応: サイアザイド系との配合剤で低カリウム予防。
用量の目安: 1日50〜100mg。
副作用:
- 高カリウム血症
- 尿路結石(シュウ酸と結合してできる)
現場のポイント:
尿路結石のリスクがある患者には注意が必要。水分摂取をしっかり指導しましょう。
アミロライド
作用機序: トリアムテレンと同じくENaC阻害。
主な適応: 低カリウム血症の是正やLiddle症候群。
用量の目安: 1日5〜10mg。
副作用:
- 高カリウム血症(特に腎機能が低下している人で起こりやすい)
現場のポイント:
腎機能の悪い患者にはごく少量で様子を見る必要があります。数日おきにカリウム値のチェックが必要です。
4. 実践での使い分けポイント

症状や患者背景によって、使うべき薬が異なります。
| 状況 | 推奨薬 | コメント |
| 心不全 | スピロノラクトン or エプレレノン | 予後改善の効果あり。副作用によって使い分け。 |
| 高カリウムを避けたい | トリアムテレン or アミロライド併用 | 低K予防としてサイアザイドと一緒に。 |
| CKD合併 | フィネレノン | 心・腎保護目的で使用。利尿効果は弱い。 |
5. 副作用への注意とモニタリング

カリウム保持性利尿剤では、特に高カリウム血症と腎機能障害に注意が必要です。
▷ 高カリウム血症
- 症状例: 筋力低下、脈が遅くなる、重症では不整脈や心停止
- 対策: 薬を始めたら3〜7日後に血液検査(K⁺、Cr)を実施し、定期的にモニタリング
▷ 腎機能障害
6. まとめ

- カリウム保持性利尿剤は、高カリウム血症という重大な副作用に注意しながら使えば、心不全やCKDの治療にとても有用です。
- 患者ごとの病態、腎機能、副作用の出やすさを考えて適切に選択・調整することが大切です。
- モニタリングを怠らず、安全に薬を使える体制を整えましょう。

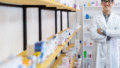

コメント