1. はじめに

夏の時期、小児科や薬局では「手足口病」「ヘルパンギーナ」「とびひ」といった小児の感染症をよく見かけます。いずれも夏場に流行しやすく、発疹や発熱を伴う点では似ていますが、原因や治療方針は異なります。そのため、症状だけで判断せず、正しい知識をもとに対応することが重要です。
薬剤師は処方内容の確認や服薬指導に加え、家庭での生活指導や再受診の目安などもわかりやすく伝える必要があります。本記事では、それぞれの病気の特徴と治療の基本方針、外用薬の選び方、服薬指導のポイントをまとめます。
2. 各疾患の特徴と治療の基本方針

手足口病
手足口病は、コクサッキーウイルスやエンテロウイルスが原因で、主に初夏から夏にかけて流行します。手のひらや足の裏、口の中に小さな水ぶくれや発疹が出現し、発熱は37〜39℃程度です。口内の水ぶくれは痛みを伴い、食事や水分摂取が難しくなり脱水のリスクがあります。
治療はウイルスに対する特効薬がないため、症状をやわらげる対症療法が中心です。解熱にはアセトアミノフェンがよく用いられます。服薬指導では、以下の点を保護者に伝えるとよいでしょう。
- 水分は少量ずつ、冷たく飲みやすい形で摂る
- 酸味や塩味の強い食品は避ける
- 尿量の減少や唇の乾燥は脱水のサインなので要注意
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナもウイルス感染症で、手足口病と同時期に流行します。ただし、手足に発疹はなく、喉の奥に小さな水ぶくれや潰瘍ができるのが特徴です。39℃以上の高熱が出ることも多く、喉の痛みから食欲が低下します。
治療は手足口病と同様に対症療法で、解熱鎮痛薬はアセトアミノフェンが一般的です。服薬指導や生活指導では、以下を意識します。
- 冷たいゼリーやアイスなど、喉越しの良い食品で水分補給
- 高熱でぐったりしている場合や呼吸が苦しそうな場合は速やかに受診
- 長引く発熱は細菌感染の合併を疑うため、再診を勧める
とびひ(伝染性膿痂疹)
とびひは細菌感染による皮膚の病気で、黄色ブドウ球菌や溶連菌が原因です。虫刺されや擦り傷を掻き壊した部分から感染が広がり、水ぶくれや膿ができ、破れると周囲に拡大します。夏の高温多湿環境では特に発症しやすくなります。
治療では、症状に応じて以下のような薬が用いられます。
- 外用抗菌薬(ムピロシン、ゲンタマイシンなど)
- 症状が広範囲または発熱を伴う場合は内服抗菌薬併用
- 強いかゆみには抗ヒスタミン薬を併用することもあり
服薬指導では、患部の清潔保持、爪を短く切ること、タオルや衣類の共有を避けることを丁寧に説明します。
3. 外用薬の選び方と注意点

外用薬の選択は、原因や症状の範囲、年齢によって変わります。
とびひでは、抗菌薬入りの軟膏が基本です。ムピロシンは黄色ブドウ球菌に有効で、MRSAにも効果があります。ゲンタマイシンは広い抗菌スペクトルを持ちますが、耐性菌リスクを避けるため短期間の使用が望まれます。塗布は1日2〜3回、患部全体を覆うようにやさしく行います。
手足口病やヘルパンギーナはウイルス性のため抗菌薬は不要で、ステロイド外用薬も原則使いません。かゆみや乾燥対策には、ワセリンなどの保湿剤を使って皮膚のバリア機能を保つことが有効です。
4. 服薬指導と生活指導のポイント

薬剤師が服薬指導を行う際には、薬の使い方だけでなく、家庭での対応方法もあわせて説明します。
手足口病やヘルパンギーナでは、脱水予防が何より重要です。水分は一度に大量ではなく、少量ずつこまめに与える方が飲みやすく、吐き戻しも防げます。経口補水液や薄めたスポーツドリンクは水分と電解質の補給に適しています。
とびひの場合は感染拡大防止が最大の課題です。タオルや寝具は個別に使用し、洗濯は分けて行います。園や学校への登園・登校は、医師の許可を得てからが望ましいと説明します。
また、再受診が必要なサインとして以下を伝えておくと、保護者の判断がしやすくなります。
- 高熱が3日以上続く
- 水分摂取が困難
- 発疹や皮膚症状が急に悪化
- 呼吸が苦しい、全身がぐったりしている
5. 薬剤師が意識すべき視点
薬剤師は、処方内容が疾患に適しているかを必ず確認し、特に小児の場合は体重や年齢による用量の違いにも注意します。OTC薬の相談を受けた際は、発熱や全身症状の有無を必ず確認し、必要に応じて受診を勧める判断力も求められます。
保護者には「自然に治ることが多いが、この症状が出たらすぐに受診してください」という具体的な説明をすることで、不安を和らげながら適切な行動を促せます。
6. まとめ

手足口病、ヘルパンギーナ、とびひは、同じ夏季に流行するものの、原因や治療方針は異なります。薬剤師は、それぞれの特徴を理解したうえで外用薬の選び方や服薬指導を行い、家庭での生活指導や再受診の目安まで含めて説明することが大切です。こうした丁寧な対応は、治癒促進だけでなく感染拡大防止にもつながります。
参考文献
- 厚生労働省. 手足口病について.
- 厚生労働省. ヘルパンギーナとは.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/herpangina.html - 公益社団法人日本皮膚科学会. 伝染性膿痂疹(とびひ)とは.
https://www.dermatol.or.jp/qa/qa13/q01.html


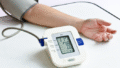
コメント