1. 高齢者・麻薬併用・妊娠…便秘薬は“状況で優先順位が変わる”
便秘薬は種類が多く、作用が似ているように思えて、実は「効く場所」も「安全性」も大きく異なります。特に高齢者施設の服薬管理、がん患者の麻薬性便秘、妊娠中の便秘相談など、背景が大きく異なる患者には同じ便秘薬を使えません。
たとえば、高齢者の慢性便秘にビサコジルを毎日出し続けて腹痛・下痢を繰り返すケース、妊娠後期の方に刺激性下剤が継続されているケース、腎機能低下者に高用量の酸化Mgが処方されているケースは、どの現場でも遭遇します。
この記事では、薬剤師が処方監査・服薬指導で迷わないように、便秘薬を「作用の違い」で明確に整理し、病態・患者背景に応じた使い分けを体系化します。
2. 便秘薬の4タイプの作用の違い

便秘薬は大きく以下の4分類に分かれます。この分類を理解すると、使い分けが非常にシンプルになります。
(1) 浸透圧性下剤
代表:酸化マグネシウム(MgO)、PEG製剤(モビコール®など)
腸管内に水分を集めて便を柔らかくし、自然な排便を促すタイプです。
刺激が弱く、高齢者・妊婦・多剤併用者でも比較的安全に使用できます。
特徴
・最も生理的
・腹痛が起こりにくい
・効果は穏やかで持続性がある
・腎障害ではMg蓄積に注意
(2) 刺激性下剤
代表:センノシド、ビサコジル、ピコスルファートNa
大腸の神経を刺激して蠕動を促すタイプで、急性の便秘に即効性があります。
しかし、腹痛・下痢が出やすく、連用で耐性が形成されやすいのが弱点です。
特徴
・即効性がある
・下剤依存や耐性が問題
・妊娠後期や腹部術後は注意
(3) 上皮機能変容薬
代表:ルビプロストン、リナクロチド
腸上皮の水分分泌を促したり、疼痛伝達を抑制したりする新しいタイプ。
特に慢性便秘や腹痛を伴う便秘、麻薬性便秘に有用です。
特徴
・自然な排便を誘導
・腹痛型便秘(IBS-C)に特に相性が良い
・妊娠中は原則避ける
(4) その他(ガス産生・浣腸)
酸化マグネシウムでも刺激性下剤でも動きにくい場合に、排便を補助する目的で使います。
3. 便秘薬比較表

便秘薬を使い分ける上で最も重要なのが「いつ効くか」。状況によって最適解は変わります。
| 分類 | 効果発現 | 持続 | コメント |
| 酸化Mg | 12–48時間 | 持続 | 慢性便秘のベースに最適 |
| PEG(モビコール) | 12–48時間 | 持続 | 小児・高齢者に最も使いやすい |
| 刺激性下剤(経口) | 6–12時間 | 短め | 就寝前に投与→翌朝効果 |
| 刺激性下剤(坐剤) | 15–60分 | 短い | 急ぎのとき |
| ルビプロストン | 24–48時間 | 持続 | 腹痛型の慢性便秘 |
| リナクロチド | 24–48時間 | 持続 | ガス・腹痛が強い患者向け |
まとめると
→急ぎ:刺激性(特に坐剤)
→長期安定:浸透圧 or 上皮機能
→痛み:リナクロチド
→麻薬性:ルビプロストン
となります。
4. 慢性便秘 vs 急性便秘の使い分け

■慢性便秘(高齢者・長期化しているケース)
最も推奨されるアルゴリズムは下記です。
1)浸透圧性下剤(酸化Mg/PEG)
2)改善しなければ 上皮機能薬(ルビプロストン/リナクロチド)
3)必要に応じて 刺激性下剤を“レスキュー的”に併用
この順は作用部位と安全性を考えると合理的です。
特に高齢者では腹痛が不穏・転倒につながりやすく、刺激性の毎日使用は避けるべきです。
■急性便秘(旅行・突然の排便停止・術後など)
・ビサコジル
・ピコスルファートNa
・坐剤
が有効です。
ただし、
“急性便秘に短期間のみ” 使用し、連用を避けるのが大前提です。
5. 妊娠・授乳の注意

妊娠中の便秘相談は現場でよくあります。
まず押さえておきたいのは次の優先順位です。
■妊娠中の第一選択
酸化マグネシウム(安全性が最も確立)
胎児への影響報告がなく、妊娠初期〜後期まで使用できます。
■避けるべき薬剤
・ルビプロストン(動物実験で胎児毒性)
・リナクロチド(吸収ほぼないが安全性データ不足)
・刺激性下剤の長期連用(子宮収縮の報告)
■授乳
酸化Mg・PEGはほぼ移行せず、授乳中も安全です。
6. 電解質異常・腎機能への影響

薬剤師が処方監査で最も注意すべきポイントです。
■酸化マグネシウム
腎排泄のため、
eGFR 30未満では高Mg血症のリスクが急増します。
症状:
・徐脈
・筋力低下
・意識障害
・呼吸抑制
腎障害患者では
・PEG
・上皮機能薬
の方が安全です。
■刺激性下剤
・腹痛
・下痢
・脱水
・低K血症
・低Na血症
高齢者は脱水→腎前性腎不全へ進むため、刺激性の常用は危険です。
■上皮機能薬
電解質異常は少ないものの、
・リナクロチド:下痢が強いと電解質変動
・ルビプロストン:悪心多め
といった副作用があります。
7. 病態別・背景別の使い分け指針
■高齢者施設
優先:PEG > 酸化Mg
腹痛が出にくく、脱水リスクも少ないため安全。
排便リズムをつくる目的で
ピコスルファートNaを週2–3回で調整する手法もよく用いられます。
■麻薬性便秘
第一選択:ルビプロストン
オピオイドによる腸管運動抑制に対してデータが豊富です。
酸化Mgとの併用は問題ありません。
■妊娠
第一選択:酸化Mg
刺激性下剤は「必要時のみ」「連用不可」と説明。
■便秘+腹痛
リナクロチドが最も効果的。
腹痛が強く、刺激性に頼って悪化しているケースで役に立ちます。
8. 減量・中止のポイント

| 症状・状況 | 想定薬剤 | 対応 |
| 強い腹痛+排便なし+嘔吐 | 刺激性下剤、いずれの下剤も | 直ちに中止。腸閉塞の可能性を考え、すぐ受診を促す。浣腸・下剤の追加はNG。 |
| 水様便が1日5回以上続く | 刺激性下剤/上皮機能薬/PEG | 一時中止または減量。脱水防止の水分補給を指導し、電解質異常が疑われる場合は受診を推奨。 |
| ふらつき・倦怠感・徐脈傾向(高齢+酸化Mg) | 酸化マグネシウム | 服用中止し、可能であれば血清Mg・Cr確認を主治医に提案。代替としてPEGや上皮機能薬を検討。 |
| 妊娠判明後も刺激性下剤を連日内服 | センノシド、ビサコジル、ピコスルファートNa | 担当医と相談の上、酸化Mgなどへの切り替えを提案。必要時のレスキュー使用にとどめる。 |
| eGFRが急に低下(30未満) | 酸化マグネシウム | 速やかに用量減量または中止し、便秘コントロールはPEGや上皮機能薬で再構成することを提案。 |
・刺激性下剤は急に止めると便秘が悪化しやすい
・酸化Mg・PEGはゆっくり減量でOK
・ルビプロストン/リナクロチドは中止で便秘が再燃しやすい
“週3回の安定排便” が得られたら減量が目安です。
9. チェックリスト/Q&A

A)5ステップ服薬指導チェックリスト(便秘薬)
- 現状把握(排便状況)
- 排便回数(週何回)/最終排便日
- 便の硬さ(ブリストルスケールで確認)
- 排便時の痛み・いきみ・残便感の有無
- 背景因子・リスク確認
- 併用薬:麻薬性鎮痛薬、鉄剤、抗コリン薬、Ca拮抗薬など
- 既往歴:腸閉塞歴、炎症性腸疾患、心不全、腎不全、妊娠の有無
- 生活習慣:水分摂取量、食物繊維、運動量、認知機能
- 薬剤の目的・期待効果を説明
- 「毎日必ず出す薬なのか」「2〜3日に1回なら良いのか」目標の設定
- 「今の薬は便を柔らかくするタイプ」「腸を動かすタイプ」など、作用の違いを簡単に説明
- 具体的な服用方法・副作用の説明
- 服用タイミング(就寝前・食後・空腹時など)
- 期待される発現時間(◯時間〜◯日)
- 腹痛・下痢・黒色便・血便・嘔吐など、受診必要な症状を共有
- フォローアップの約束をする
- 「1〜2週間後に、排便回数と便の硬さを教えてください」
- 高齢者施設なら「排便表への記録」を依頼
- 悪化時の連絡先(診療所・薬局)を確認
B)よくある質問と回答(Q&A×5:各150字目安)
Q1. 妊娠中ですが、酸化マグネシウムは飲み続けても大丈夫ですか?
A1. 酸化マグネシウムは腸の中で作用し、全身への吸収は少なく、妊娠中でも比較的安全とされています。ただし、自己判断で量を増やしすぎると下痢や高マグネシウム血症のリスクがあるため、医師や薬剤師と相談しながら最小限の量で使うことが大切です。
Q2. 刺激性下剤を毎日飲んでいますが、やめると全く出なくなります。大丈夫でしょうか?
A2. 刺激性下剤を長期間使い続けると、腸が薬に頼りやすくなり、自然な動きが弱くなることがあります。少しずつ減量しながら、酸化マグネシウムやPEGなど“便を柔らかくする薬”に切り替えることで、腸の負担を減らすことができます。医師と計画的に調整しましょう。
Q3. 麻薬性鎮痛薬を飲み始めてから便秘がひどくなりました。どの薬が合いますか?
A3. オピオイドによる便秘には、腸の分泌を増やすルビプロストンなど、専用の薬が有効な場合があります。酸化マグネシウムと組み合わせることも多いです。刺激性下剤だけで何とかしようとすると腹痛や下痢が強くなることがあるので、処方薬で適切な調整を受けることが重要です。
Q4. 高齢の親が便秘で刺激性下剤を飲んでいますが、時々お腹が痛くてトイレで転びそうになります。
A4. 高齢者に刺激性下剤を連日使うと、腹痛や急な下痢でトイレに急いで転倒するリスクがあります。PEGや酸化マグネシウムなど、より穏やかな薬をベースにして、刺激性下剤は“どうしても出ない時の予備”にする方が安全です。介護スタッフとも相談し、排便表をつけて調整するのがおすすめです。
Q5. 便秘薬を飲んで下痢になった時は、すぐに中止した方がいいですか?
A5. 水のような下痢が続く場合は、脱水や電解質異常の危険があるため、一度内服を中止して様子を見ることが必要です。特に血便・強い腹痛・嘔吐を伴うときは腸閉塞や感染性腸炎など、別の病気の可能性もあるので速やかに受診を勧めます。再開時は量を減らして慎重に使うことがポイントです。
10. まとめ:薬剤師が今日から使える要点3つ

- 便秘薬は“浸透圧→上皮機能→刺激性”の順で使い分けると安全にコントロールできる。
- 妊娠・高齢・腎障害では優先薬と禁忌薬が明確。
- 刺激性下剤は急性便秘の短期用。慢性便秘のベースは酸化Mg・PEG・上皮機能薬。
参考文献
便通異常症診療ガイドライン2023―慢性便秘症
慢性便秘症
小児慢性機能性便秘症ガイドライン
自分の思うような仕事ができないと思ったら
便秘治療は、患者さんの生活の質だけでなく、薬剤師自身の業務負担にも直結するテーマです。
とくに高齢者施設や外来での排便コントロールは、薬剤の選択・調整・説明が多岐にわたり、
「今の職場では十分に時間が取れない…」
「もっと専門性を活かして働きたい」
と感じる場面も少なくありません。
もし今の働き方に少しでも負担や不安を感じているなら、
“職場を変える”ことも薬剤師としての大切な選択肢のひとつです。
ファルマスタッフは、調剤薬局・病院・在宅など、
薬剤師の専門性を発揮できる職場を多数扱っており、
勤務条件の交渉まで代行してくれるため、働きやすさの向上を実感しやすい点が特徴です。
無理に転職する必要はありませんが、
「今より良い環境があるか少し見てみたい」という段階でも利用できます。
働き方について悩みがある方は、まずは求人をチェックしてみても良いかもしれません。


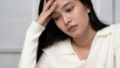
コメント