春の花粉症シーズン、薬局では「眠くならない薬がいい」「子どもに使える薬は?」「運転しても大丈夫?」といった相談が一気に増えます。
しかし第1世代と第2世代では、鎮静性・抗コリン作用・妊娠授乳での扱い・小児の安全性が大きく異なります。
この記事では“薬剤師が現場で迷わず説明できる”ように、抗ヒスタミン薬の使い分けについて解説します。
2. H1受容体拮抗薬の基本作用

アレルギー性鼻炎や花粉症では、アレルゲン曝露により肥満細胞からヒスタミンが放出され、H1受容体を刺激することで“くしゃみ・鼻水・掻痒が起こります。
抗ヒスタミン薬は
- H1受容体をブロックし、症状を軽減する薬
ですが、世代により“中枢移行性”が異なるため、眠気などの副作用に差が生じます。
3. 第1世代と第2世代の鎮静性の違い

● 第1世代:眠気・抗コリン作用が強い
第1世代は脂溶性が高く、血液脳関門を通過しやすいため、
- 強い鎮静性
- 注意力・集中力の低下(自覚ない作業能率低下)
- 口渇・便秘・尿閉(抗コリン作用)
が問題となり、日中の服薬には向きません。
● 第2世代:非鎮静性が中心。運転可否の差は薬剤ごと
第2世代は脳移行が少なく、
- 眠気が少なく仕事・運転と両立しやすい
- 抗コリン作用が弱い
- 小児・妊娠授乳で使いやすい薬も多い
といった特徴があります。ただし、第2世代でも
- セチリジン
- レボセチリジン
- オロパタジン
など「運転禁止」の注意文言がある薬もあり、“第2世代=絶対に眠くならない”わけではない点は重要です。
4. 妊娠・授乳での注意点

妊娠・授乳では「有益性>危険性」の原則で判断します。
多くの第2世代は添付文書で「有益性が上回る場合に投与」とされ、臨床ではフェキソフェナジンなど非鎮静性薬を中心に処方されやすい傾向です。
一方、ロラタジンは「妊婦に投与しないことが望ましい」と明確に強い表現があり、説明が必要です。
授乳では母乳移行が完全には否定できないため、服薬後の授乳タイミング調整(母乳バンク方式)などを検討します。
5. 小児での使い分け

● 第1世代は小児で興奮・けいれんリスクがある
特に乳幼児では中枢刺激で興奮したり、けいれん閾値が下がる可能性があるため使用を避けたい場面が多いです。
● 第2世代は小児用量が整備されている薬が多い
- フェキソフェナジン(7歳〜)
- ベポタスチン(7歳〜)
- オロパタジン(小児量あり)
- セチリジン(6か月〜適応あり)
小児は体重換算での用量調整が必要な薬もあるため、添付文書準拠が必須です。
6. 抗コリン作用と相互作用(実務で重要)

● 抗コリン作用
第1世代で強く、以下の患者で注意:
- 緑内障
- 前立腺肥大
- 便秘・イレウスリスク
- 高齢者(せん妄・転倒の危険)
● 相互作用
- 中枢抑制薬(睡眠薬・抗不安薬・アルコール)で眠気増強
- 抗コリン薬と併用で尿閉・せん妄リスク↑
- フェキソフェナジン:フルーツジュースで吸収低下(OATP阻害)
- エバスチン・ロラタジン・ルパタジン:CYP3A4阻害薬で濃度上昇
薬剤ごとの相互作用は「比較表」の項目に個別に記載しています。
▼ 抗ヒスタミン薬の比較表

抗ヒスタミン薬 比較表(第1世代/第2世代)
| 一般名 | 商品名(代表) | 作用機序 | 代謝酵素・トランスポータ | 主な相互作用 | 半減期と服用時刻 | エビデンス・特徴(鎮静性含む) | 注意点(高齢/妊娠授乳/腎肝障害) |
| クロルフェニラミン(第1世代) | ポララミン等 | H1拮抗 中枢移行↑ | 肝代謝 | 中枢抑制薬・抗コリン薬で副作用↑ | t1/2 12–24h/1日2–3回 | 鎮静性強い・抗コリン作用強い | 高齢者でせん妄・転倒。妊婦は有益性投与。緑内障・前立腺肥大で注意 |
| ジフェンヒドラミン(第1世代) | レスタミン等 | H1拮抗 | 肝代謝 | 中枢抑制薬で眠気増強 | t1/2 4–9h/1日3–4回 | 強い鎮静性。不眠・乗り物酔い用途も | 高齢者/小児で中枢刺激。妊婦は有益性投与 |
| フェキソフェナジン(第2) | アレグラ | 末梢H1拮抗 | 代謝ほぼなし/OATP・P-gp | フルーツジュースで吸収↓、制酸薬でAUC↓ | t1/2 14h/1日2回 | 非鎮静性の代表。運転注意文言なし | 腎障害で半減期延長。妊娠授乳は有益性投与 |
| ロラタジン(第2) | クラリチン | H1拮抗 | CYP3A4/2D6 | マクロライド・アゾール系で濃度↑ | t1/2 8h/1日1回 | 非鎮静性。運転注意文言なし | 妊婦“投与しない方が望ましい” |
| デスロラタジン(第2) | デザレックス | H1拮抗 | 肝代謝 | CYP阻害薬で濃度↑可能性 | t1/2 23h/1日1回 | 非鎮静性。効果発現が速いとされる | 肝腎障害で慎重投与 |
| ビラスチン(第2) | ビラノア | H1拮抗 | 代謝ほぼなし/P-gp | グレープフルーツで吸収↓ | t1/2 10.5h/空腹時1日1回 | 非常に非鎮静性。運転注意なし | 腎障害で血中濃度↑ |
| セチリジン(第2) | ジルテック | H1拮抗 | 腎排泄 | 中枢抑制薬で眠気↑ | t1/2 8h/1日1回 | 軽度~中等度の鎮静性 | 腎障害で減量。眠気で仕事影響 |
| レボセチリジン(第2) | ザイザル | H1拮抗 | 腎排泄 | 中枢抑制薬で眠気↑ | t1/2 7.3h/1日1回 | 運転禁止文言あり | 腎障害で用量調整必須 |
| オロパタジン(第2) | アレロック | H1拮抗+遊離抑制 | 肝腎排泄 | 中枢抑制薬で眠気↑ | t1/2 8–10h/1日2回 | 運転禁止。即効性あり | 妊娠授乳は有益性投与 |
| ベポタスチン(第2) | タリオン | H1拮抗 | 腎排泄主体 | 中枢抑制薬で眠気↑ | t1/2 2–3h/1日2回 | 非鎮静性〜軽度鎮静性。使いやすい | 腎障害で慎重。7歳以上小児可 |
| エバスチン(第2) | エバステル | H1拮抗 | CYP2J2/3A4 | CYP3A4阻害薬で濃度↑ | 活性体t1/2 15–19h/1日1回 | 非鎮静性だが運転注意あり | 肝障害で濃度↑ |
| ルパタジン(第2) | ルパフィン | H1拮抗+PAF拮抗 | CYP3A4 | マクロライド・GFJで濃度↑ | t1/2 5–6h/1日1回 | 非鎮静性だが運転注意あり | 肝腎障害で慎重 |
7. 病態別・患者背景別の使い分け指針

● 花粉症シーズン(軽症〜中等症)
- 第2世代・非鎮静性を基本
フェキソフェナジン、ビラスチン、ロラタジン、デスロラタジンなど。
● 鼻漏・掻痒が強い/即効がほしい
- 若干鎮静性のある
- セチリジン
- オロパタジン
- レボセチリジン
が「効き目を実感しやすい」ことも多い。ただし運転禁止の説明は必須。
● 運転・集中作業がある患者
- フェキソフェナジン・ビラスチン・ロラタジン・デスロラタジン:最有力
- レボセチリジン・オロパタジン・エバスチンは注意文言があり避ける。
● 小児
- 第2世代を優先
- 第1世代は興奮・けいれんリスクで避ける。
● 高齢者
- 第1世代はほぼ禁忌に近い扱い
(せん妄・転倒・尿閉・便秘を強く増悪) - 第2世代も眠気確認を必ず。
● 妊娠・授乳
- フェキソフェナジン・セチリジン・デスロラタジンなどを中心に「有益性>危険性」で使用
- ロラタジンは添付文書の表現が強いため説明が必須。
8. 減量・中止のポイント

- 症状が落ち着き、再発リスクが少なければ漫然と継続しない
- 眠気・作業能率低下・せん妄・便秘・尿閉などが出たら:
① 非鎮静性への切り替え
② 併用薬(睡眠薬・抗コリン薬)の見直し
③ 服用時刻変更(夜のみ)などを検討
9. 現場で使える指導例(実務箱)
■ 服薬指導5ステップ
- 症状タイプ(くしゃみ・鼻水・掻痒・鼻閉)を確認
- 運転・仕事・学業など眠気が問題になるかを確認
- 年齢・妊娠授乳・基礎疾患(前立腺肥大・緑内障)を確認
- 併用薬(睡眠薬・抗不安薬・抗コリン薬・抗真菌薬)を確認
- 効果と副作用(眠気・口渇・排尿障害)のモニタを説明
■ よくある質問Q&A(簡易版)
- Q:眠くならない薬はどれ?
→ フェキソフェナジン・ビラスチン・ロラタジン・デスロラタジンが非鎮静性です。 - Q:花粉症の薬はどれが一番強い?
→ 効果は大きな差はありません。眠気の有無・回数・生活背景で選びます。 - Q:子どもにはどれを使えばいい?
→ 第2世代を基本に、小児用量がある薬(フェキソフェナジン、オロパタジン、セチリジンなど)から選びます。 - Q:運転しても大丈夫?
→ 薬によっては“運転禁止”。非鎮静性を選んでも、最初の数日は眠気を自己チェックしてください。 - Q:授乳中に飲んでいい?
→ 多くは可能ですが、授乳前の服薬や時間調整でリスクを下げられます。
10. まとめ(要点3つ)
- 基本は第2世代(特に非鎮静性)の使用が推奨。
- 第1世代は眠気・抗コリン作用が強く、高齢者・小児では避ける。
- 運転・妊娠授乳・腎肝障害など、患者背景で最適な薬が大きく変わる。
「忙しすぎて丁寧な服薬指導ができない…」と感じたら

抗ヒスタミン薬は薬剤差が大きく、運転注意や小児用量など説明ポイントも多い薬です。
本当は一人ひとりに合わせて丁寧に声かけしたいのに、
- 来局が集中して説明が駆け足になる
- 人手が足りず相談対応に余裕がない
- 調剤に追われて患者さんの不安を拾いきれない
そんな“現場のしんどさ”を感じている人も多いと思います。
もし今の環境で無理が続くなら、もっと服薬指導に時間を割ける職場や、働き方を整えやすい環境に移るのも一つの手です。
ファルマスタッフなら、希望条件をもとに「今より無理なく働ける職場」を一緒に探せます。
まずはどんな選択肢があるかだけでも見ておくと、次の一手が選びやすくなります。

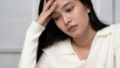

コメント