はじめに

妊娠中や授乳中は「この薬、飲んでいいの?」「赤ちゃんに影響はないのかな?」と不安になることが多いものです。多くの人が「薬は全部ダメ」と思い込んでしまいがちですが、それは正しい理解ではありません。実は、きちんと確認すれば飲める薬もあるのです。
この記事では、薬剤師の立場から妊娠中・授乳中の薬の考え方や、飲める薬・避けるべき薬の例、そして信頼できる情報源として国立成育医療研究センターの資料の活用方法について、わかりやすくお伝えします。
妊娠中・授乳中の薬は全部ダメじゃない

妊娠中・授乳中でも、適切な薬なら使用できることがあります。ただし、薬を飲む・飲まないを自己判断するのはとても危険です。赤ちゃんの健康だけでなく、母体の健康を守るためにも、医師や薬剤師に相談して決めることが重要です。
妊娠の時期によっても薬の影響は異なります。妊娠初期(12週まで)は赤ちゃんの体の基本が作られる時期で、薬の影響を最も受けやすいとされています。中期(13〜27週)は安定期に入りますが、薬による成長への影響がないわけではありません。後期(28週以降)は分娩に影響する薬が出てくる場合があります。
一方、授乳中は母乳を通じて薬の成分が赤ちゃんに届く可能性がありますが、多くの場合は移行する量がごくわずかで、授乳を続けながら薬を使えることも多いのです。
国立成育医療研究センターの「使える薬」情報を活用しよう

授乳中に薬を使うとき、頼りになるのが国立成育医療研究センター・妊娠と薬情報センターです。
このセンターは、妊婦さんや授乳中の方が安心して治療を受けられるように、薬ごとの安全性情報を公開しています。
公式サイトはこちらです:
👉 国立成育医療研究センター・妊娠と薬情報センター
サイトには、よく使われる薬の安全性についてわかりやすく整理された資料があります。たとえば、以下のような薬が「比較的安全」とされています。
授乳中に使える薬の例(国立成育医療研究センター資料より)
| 分類 | 具体例(商品名の一例) |
| 解熱鎮痛薬 | アセトアミノフェン(タイレノールなど) |
| 抗アレルギー薬 | ロラタジン(クラリチン)、セチリジン(ジルテック) |
| 胃薬 | ファモチジン(ガスター) |
| 便秘薬 | 酸化マグネシウム(マグミット) |
| 咳止め | デキストロメトルファン(メジコンなど) |
ただし、個々の体質や症状によって使えない場合もあります。最終的な判断は必ず医療者に相談してください。
薬を選ぶときに大切なこと

薬を選ぶとき、「薬そのものが悪い」と考えて必要な治療を避ける人もいますが、それは誤解です。病気を放置することで、母体や赤ちゃんにより大きなリスクが生じることもあります。
例えば、高熱を放置すれば流産や早産のリスクが高まりますし、重い感染症を治療しないと命に関わる場合もあります。薬の副作用リスクと病気のリスクをしっかり比べて、必要なら正しく薬を使うことがとても重要です。
具体的には、軽い頭痛や発熱はまず冷やす・水分補給・休息を優先しますが、必要な場合はアセトアミノフェンを使います。花粉症やアレルギー症状は、ロラタジン(クラリチン)、セチリジン(ジルテック)といった薬が使える場合があります。胃の不調や胸やけでは食事の見直しを行い、必要ならファモチジン(ガスター)を使います。
こうした選択は自己判断では難しいため、必ず医師や薬剤師と相談してください。
よくある質問と注意点

妊娠中・授乳中の薬については、患者さんからよく以下のような質問があります。
「授乳中に風邪薬を飲んでも大丈夫ですか?」と聞かれることがありますが、薬によっては問題ありません。ただし成分によっては母乳に移行しやすいものもあるので、必ず確認が必要です。
「妊娠中の市販薬は大丈夫ですか?」という質問も多いですが、アセトアミノフェンは比較的安全とされますが、NSAIDs(イブプロフェンなど)は妊娠後期では避ける必要があります。
「漢方薬は安全ですか?」とよく誤解されますが、自然由来だからといって安全とは限りません。成分によっては妊娠・授乳に影響するものもあるため、使用前に必ず医療者に相談してください。
情報収集のときは信頼できる情報源を使おう

インターネットにはさまざまな情報があふれていますが、古かったり誤っていたりするものもあります。正確な情報を確認したいときは、国立成育医療研究センターの「妊娠と薬情報センター」を活用してください。
この公式サイトでは、薬ごとの安全性情報やよくある質問、注意点がまとめられています。医師・薬剤師も日常的に参考にしている公的機関の情報なので、ぜひ一度チェックしてみてください。
まとめ

妊娠中・授乳中の薬の使用は慎重になる必要がありますが、「薬を一切使わないこと」が正しいわけではありません。母体と赤ちゃんの健康を守るためには、必要なときは正しく薬を使うことが大切です。
- 自己判断せず、医師・薬剤師に相談する。
- ネット情報は鵜呑みにせず、信頼できる公的情報を活用する。
- 国立成育医療研究センターの情報をチェックする。
正しい知識と専門家の助言を活用し、不安を減らして安心できる治療を受けましょう。あなたと赤ちゃんの安全を守るために、決して一人で抱え込まず、相談する勇気を持ってください。
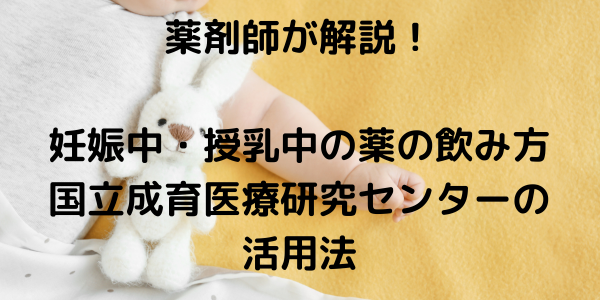
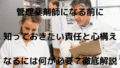
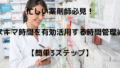
コメント