飲酒習慣を持つ患者に薬剤師ができる安全管理ガイド
はじめに──なぜ「お酒 × くすり」に注意が必要なのか

お酒(アルコール)は日常的に飲まれる嗜好品ですが、実は多くの医薬品と「相性が悪い」ことがあります。特に、高齢者や持病を持つ方、複数の薬を服用している方では、アルコールが薬の効き方や副作用の出方に大きな影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、「薬を飲んだ日にお酒を飲んでしまったら、急にふらついて転倒した」「肝臓の数値が悪化していた」などのトラブルは、薬剤師の現場でもしばしば聞かれる事例です。
この記事では、なぜアルコールと薬の組み合わせが危険なのか、その理由や具体的な薬の例、そして薬剤師がどのように患者に声かけすべきかについて解説していきます。
1|どうしてアルコールと薬が「合わない」のか?──相互作用のメカニズム

アルコールは体内で「異物」として代謝(=分解・排出)されます。この代謝の仕組みは、実は多くの薬とも共通しており、以下のような点で薬と“ぶつかって”しまうのです。
| 観点 | 代表的なしくみ | 臨床上の問題(例) |
| 薬の分解ルートが重なる(=代謝競合) | アルコールと同じ酵素(CYP)で薬を分解し合う | 薬が効きすぎたり、逆に効かなかったりする |
| 薬の作用を強めてしまう(=薬力学的相互作用) | 両方とも脳を抑える作用がある | 呼吸が弱くなる、意識がもうろうとする |
| 肝臓や胃腸へのダメージが重なる | 両者とも肝臓に負担をかける | 肝障害、胃潰瘍、出血などが起きやすくなる |
| アルコールの量で反応が変わる | 飲み方(大量・慢性・断酒)で酵素の働きが変化 | 血中濃度が安定しなくなる |
🔍 ポイント:薬の「効き方」を決めるのは、体の中でどう代謝されるか、そしてその薬がどんな作用をもたらすか。アルコールはこれらの“両方”に干渉するため、注意が必要です。
2|具体的な薬とその注意点(代表的なものを紹介)

ここからは、患者さんがよく使う代表的な薬と、アルコールとの危険な組み合わせについて説明します。
① 中枢神経系の薬(睡眠薬、抗不安薬、オピオイドなど)
これらは「脳の働きをゆるめる」薬です。眠気を起こしたり、気分を落ち着かせる作用がありますが、アルコールも同じように中枢神経を抑える働きがあります。
併用すると…
- 意識がもうろうとしたり
- 呼吸が浅くなったり
- 転倒・事故のリスクが急上昇
薬剤師としての注意点:
「薬を飲んだ日は飲酒を控えてください」と明確に伝えましょう。
② 解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン、NSAIDs)
熱や痛みをとるための薬でも、アルコールと相性が悪いものがあります。
- アセトアミノフェン:飲酒により肝臓での解毒が追いつかず、重い肝障害を起こすことがあります。
- NSAIDs(イブプロフェンなど):胃の粘膜を荒らす副作用があり、そこにアルコールが加わると胃潰瘍のリスクが高まります。
アドバイス例:
「空腹時の服用+お酒」は避け、できるだけ食後に服用するよう伝えましょう。
③ 抗菌薬の一部(メトロニダゾールなど)
この薬は、お酒と一緒に飲むと「ジスルフィラム様反応」という強い副作用を引き起こすことで知られています。
症状の例:
- 顔のほてり、頭痛、吐き気、動悸など
- 飲酒から1〜2日後でも反応が起きることがあります
患者への伝え方:
「この薬を使っている間と、その後2日は禁酒です」と具体的に日数を伝えると安心されます。
④ 抗糖尿病薬(インスリン、SU薬など)
アルコールは、肝臓での糖新生を抑制する可能性があるので、血糖値が不安定になるかもしれません。
特に問題になるのは…
- 空腹時の飲酒
- 食事を取らずにお酒だけ飲むこと
アドバイス:
「お酒を飲むなら食事と一緒に、できれば少量で」と伝えるのが現実的です。
⑤ ワルファリン・DOACなどの抗凝固薬
血液をサラサラにする薬は、アルコールで作用が変動することがあります。
- ワルファリンは酵素の働きに影響されやすく、PT-INR(出血リスクを示す指標)が大きく変わることも。
- DOACは、アルコールの胃腸障害と重なることで消化管出血のリスクが上がるとされています。
対応例:
「普段から飲酒する方は、1日○杯まで」など量を具体的に伝えると良いです。
3|患者指導で大切な3つのステップ

ステップ1|飲酒量を「数値化」して確認する
ただ「お酒を飲みますか?」と聞くだけでは不十分です。
「週に何日飲みますか?」「1日に何杯くらいですか?」など、具体的に聞くようにしましょう。
✨目安:「1ドリンク」=純アルコール20g(ビール中瓶1本、日本酒1合)
ステップ2|リスクを整理するチェックシートを使う
・週あたりの飲酒日数
・1回の飲酒量
・年齢、肝機能、併用薬の数
などを一覧にして、どのくらいリスクが高いかを整理します。
ステップ3|無理のない「代替案」を一緒に考える
「今日飲まなかったから、明日たくさん飲もう」は逆効果です。
患者さんの生活を尊重しながら、以下のような提案をしましょう。
- 休肝日を週2回作る
- ノンアルコール飲料に置き換える
- 食事と一緒に少量だけ飲む など
4|特に注意すべき人たち

| 対象 | なぜ注意が必要? | 薬剤師の対応例 |
| 高齢者 | 代謝が遅く、薬もお酒も効きやすい | ほんの少量でも影響が大きいことを説明 |
| 肝臓が弱い人・低栄養の人 | 解毒する力が弱いため、薬が蓄積しやすい | 血液検査の結果もふまえて判断をサポート |
| 妊娠・授乳中の方 | 胎児や赤ちゃんへの影響が強い | 原則「完全禁酒」をすすめる |
まとめ|薬剤師が“今日から”できること

- 飲酒習慣を「数値」で把握する
- 薬の代謝や作用に注意し、飲酒リスクのある薬をチェック
- 患者さんに寄り添って「現実的なアドバイス」を伝える
アルコールとの併用は、患者さん自身が「少しくらいなら大丈夫」と思い込みがちな部分です。
だからこそ、薬剤師がわかりやすく、そして具体的に伝えていくことが大切です。
参考URL
e-ヘルスネット「飲酒量の単位(純アルコール量)」
PMDA 添付文書「メトロニダゾール:ジスルフィラム様反応に関する注意喚起」2024/04 改訂

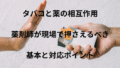
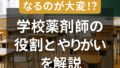
コメント