はじめに:整腸剤はどう違うの?

腸内環境を整える「整腸剤」は、薬局や病院でよく目にするおなじみの薬です。便秘や下痢、食生活の乱れによる腸内環境の不調に対して処方・推奨されることが多く、一般用医薬品(OTC)として市販されているものから医療用まで幅広く存在します。
しかし、一口に「整腸剤」といっても、含まれる菌の種類や作用の仕組み、得意とする症状や対象年齢はそれぞれ異なります。薬剤師としては「どの薬がどんな患者さんに適するのか」を理解しておくことが大切です。
代表的な整腸剤としてよく処方・販売されるのが、ビオフェルミン、ビオスリー、ミヤBM、ラックビーです。本記事では、それぞれの特徴や作用の違いを比較し、薬剤師の視点から整理していきます。
各整腸剤の特徴と作用機序

ビオフェルミン
- 主成分:乳酸菌(製品により異なる。例:フェカリス菌、アシドフィルス菌、ビフィズス菌など)
- 作用:乳酸菌を補給することで腸内を弱酸性に保ち、有害菌の増殖を抑える。腸内フローラのバランスを改善する。
- 特徴:
- 小児(OTCのS錠は5歳以上から)から高齢者まで幅広く使用可能。
- マイルドな整腸作用で安全性が高い。
- 薬剤師の視点:
- 軽度の便通異常や日常的な整腸目的に使いやすい。
- 相互作用の心配がほとんどなく、生活習慣改善と併用しやすい。
ビオスリー
- 主成分:乳酸菌、酪酸菌、糖化菌の3種類
- 作用:
- 乳酸菌:腸内を酸性に保ち、有害菌を抑制。
- 酪酸菌:短鎖脂肪酸(酪酸)を産生し、腸粘膜のエネルギー源となる。
- 糖化菌:アミラーゼを産生し、乳酸菌の産生を促進。
- 特徴:複数の菌を組み合わせることで相乗効果を期待できる。
- 薬剤師の視点:
- 「下痢と便秘を繰り返す」など腸内環境が不安定な患者に有用。
- 消化不良や食欲不振を伴うケースで処方されることが多い。
ミヤBM
- 主成分:宮入菌(Clostridium butyricum MIYAIRI株)
- 作用:
- 芽胞形成菌で胃酸に強く、生きたまま腸に届く。
- 腸内で発芽・増殖し、酪酸を産生。
- 酪酸は大腸上皮細胞の栄養源となり、腸粘膜の修復や抗炎症作用をサポート。
- 特徴:
- 医療用で広く処方されており、抗菌薬との併用にも耐性がある。
- 適応外であるが抗菌薬関連下痢や過敏性腸症候群(IBS)にも臨床実績がある。(エビデンスは少ない)
- 薬剤師の視点:
- 「抗菌薬を飲むと下痢しやすい」という患者に特に有用。
- 腸内フローラの乱れを修正する力が強い。
ラックビー
- 主成分:ビフィズス菌(Bifidobacterium breve など)
- 作用:
- 善玉菌を増やし、乳酸や酢酸を産生して腸内を弱酸性に保つ。
- 病原菌の増殖を抑制し、便通を整える。
- 特徴:
- 小児・乳児を含め幅広い年齢層で使用可能。
- 特に小児科領域で処方されることが多い。
- 薬剤師の視点:
- 小児の便秘や消化不良に頻用される。
- 安全性が重視される場面で選ばれやすい。
整腸剤の作用の違いと使い分け

整腸剤の効果は「どの菌を補うか」で大きく変わります。
- ビオフェルミン:
→ マイルドな整腸効果。日常的な整腸や軽度の便通異常に。 - ビオスリー:
→ 複合菌による相乗効果。消化不良や便通異常が続くケースに。 - ミヤBM:
→ 芽胞菌で胃酸に強く、抗菌薬使用中でも安定して効果を発揮。抗菌薬関連下痢やIBSに。 - ラックビー:
→ 小児・乳児の腸内環境改善に強み。小児科での処方頻度が高い。
薬剤師としては、患者背景(年齢・症状・併用薬)を見極めたうえで提案 することが重要です。例えば、抗菌薬を処方されている高齢患者にはミヤBM、小児の便秘にはラックビー、食欲不振が続く成人にはビオスリー、といった具合に選択が変わってきます。
まとめ:どれを選ぶ?

整腸剤は「腸内環境を整える」という点で共通していますが、菌種ごとに得意とする分野が異なります。
- ビオフェルミン:幅広い層に安全でマイルドな整腸剤。
- ビオスリー:消化不良や便通異常に適応。
- ミヤBM:抗菌薬使用中や下痢傾向のある患者に。
- ラックビー:小児・乳児の腸内改善に強み。
患者さんが自己判断で選ぶのではなく、症状や服薬状況を確認した上で薬剤師・医師と相談することが望まれます。また、整腸剤だけに頼るのではなく、食物繊維や発酵食品の摂取、生活習慣の改善も同時に意識することで、より効果的な腸内環境改善が期待できます。


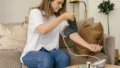
コメント