高齢者の「寝たきり」や「要介護化」の大きな要因であるサルコペニア(加齢に伴う筋肉量・筋力の低下)。この対策は医療・介護の現場にとって重要なテーマです。
しかし、薬剤師は運動や身体評価に直接関わることは難しく、理学療法士や管理栄養士とどう連携するかがカギとなります。本記事では、薬剤師が安全に・現実的に関与できる範囲を整理し、サプリメント・医薬品・漢方薬の適正使用を中心に、多職種との連携モデルを紹介します。
サルコペニアとは?定義と背景を正しく理解する

サルコペニアは「筋肉量の減少」に加え、「筋力の低下」や「歩行速度の低下」を伴う状態です。診断には、国際的に以下のような評価が用いられます。
- SARC-F:問診形式の簡易スクリーニング
- 握力・椅子立ち上がりテスト:筋力評価
- BIA法やDXA法:筋肉量の計測
特に後期高齢者、糖尿病や心不全、慢性腎不全の患者はリスクが高く、在宅医療の中でも注意が必要です。
薬剤師が関与すべき理由とタイミング

薬剤師がサルコペニア支援に関与すべき理由は、単に「栄養と薬の知識があるから」ではありません。薬剤師は、他職種と違う視点で次のような重要な役割を担えます。
- 筋力低下を助長する薬剤の見直し(例:過剰な利尿薬、ベンゾジアゼピンなど)
- サプリメントや漢方薬に関する相談対応
- 管理栄養士や理学療法士との情報連携による安全な介入
薬剤師が“すべてを抱える”のではなく、“連携の要”として機能することが現場で求められています。
最低限押さえておきたい栄養とサプリメント

栄養はサルコペニア対策の基盤ですが、薬剤師がサプリメントを積極的に提案する場面は限られます。栄養の補強のためにサプリメントの使用を相談された場合、最低限の知識があった方がいいでしょう。下記サプリメントについては、患者や家族から相談された際に備えておきたい基本的な知識です。
- プロテイン(ホエイ・ソイ)
たんぱく質の補給源。摂取目安は体重1kgあたり1.2~1.5g/日。高齢者では食事から十分な量を確保しづらいため、栄養士と連携して補完します。 - HMB(β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)
筋分解の抑制作用が期待され、サルコペニア対策の研究も進んでいます。1.5~3g/日が目安。 - ビタミンD
骨と筋肉の健康に関与。800~1,000IU/日程度の補充が一般的ですが、併用薬や腎機能によっては慎重な管理が必要です。
▶ 薬剤師が注意すべき点
腎機能低下がある場合はプロテインの過剰摂取が有害となることもあります。また、サプリメントは医薬品との相互作用や重複リスクもあるため、確認と指導が不可欠です。
医薬品による介入はどう位置づけるか?

現在、サルコペニアに対して明確に承認された治療薬はありませんが、以下のような選択肢が検討されることがあります。
- アナボリックステロイド/テストステロン補充療法
重症サルコペニアでの適応例あり。ただし副作用(多血症、肝機能障害など)に注意。 - SARM(選択的アンドロゲン受容体モジュレーター)など開発中の薬剤
今後の実用化が期待されており、薬剤師として情報のアップデートが重要です。
▶ 薬剤師の関わり方
処方提案というよりは、副作用モニタリングや情報提供を通じた「チームの一員」としての貢献が現実的です。
食欲・消化機能の改善に役立つ漢方薬

高齢者では「そもそも食べられない」「胃もたれしやすい」といった課題もあります。栄養摂取の土台を支えるために、以下の漢方薬が有効となる場合があります。
- 人参養栄湯(にんじんようえいとう)
倦怠感や食欲不振に。全身状態を底上げし、栄養介入の基盤をつくります。 - 六君子湯(りっくんしとう)
胃腸虚弱、食後の膨満感などを改善し、経口摂取量の増加につながります。
▶ 注意すべき点
他の医薬品との相互作用、利尿薬との併用による電解質異常など副作用には注意が必要。保険適応かどうかも確認を。
運動・評価はPTに任せ、薬剤師は“安全管理と連携”を

筋力評価や運動療法の実施には転倒リスクが伴うため、薬剤師が独自に行うのは現実的ではありません。30秒椅子立ちテスト(CS-30)や5回椅子立ち上がりテスト(5-CST)は、主に理学療法士(PT)が安全に実施します。
薬剤師ができるのは、その測定結果を活かして以下のような介入を行うことです。
- 降圧薬による起立性低血圧や利尿薬による脱水リスクの評価と助言
- 糖尿病治療薬使用中の患者への運動前後の低血糖対策の助言
- 運動後の栄養補給タイミングに合わせたサプリ・漢方の調整(※管理栄養士と連携)
多職種連携の実践プロトコル

- 退院時カンファレンス
医師・PT・管理栄養士・薬剤師が集まり、患者の身体機能・栄養状態・服薬状況を確認し、それぞれの役割分担を明確化。 - 在宅導入フェーズ
PTが初期評価を実施。薬剤師は処方薬・栄養補助食品・サプリメントの整理とアドヒアランス支援を行う。 - 月次モニタリング
SARC-FやCS-30などの再評価に応じ、薬剤師が薬学的・栄養面から処方の見直しを提案。
ケーススタディ:独居82歳女性への支援

- 状況:独居・心不全あり・利尿薬・糖尿病薬服用。食欲不振。
- 評価:PTがCS-30を実施し、10回(基準未満)→サルコペニアの疑い
- 介入内容:
- 利尿薬の減量提案 → 起立性低血圧予防
- 人参養栄湯+ホエイプロテインの導入
- 管理栄養士と協働でONS(経口栄養補助食品)の導入
- 3か月後:
- CS-30=15回に改善、体重+1.8kg、転倒ゼロ
このように、薬剤師は「運動させる」のではなく、「運動できる体の土台を整える」ことに貢献できます。
まとめ|薬剤師は“ハブ”としてチームに貢献できる
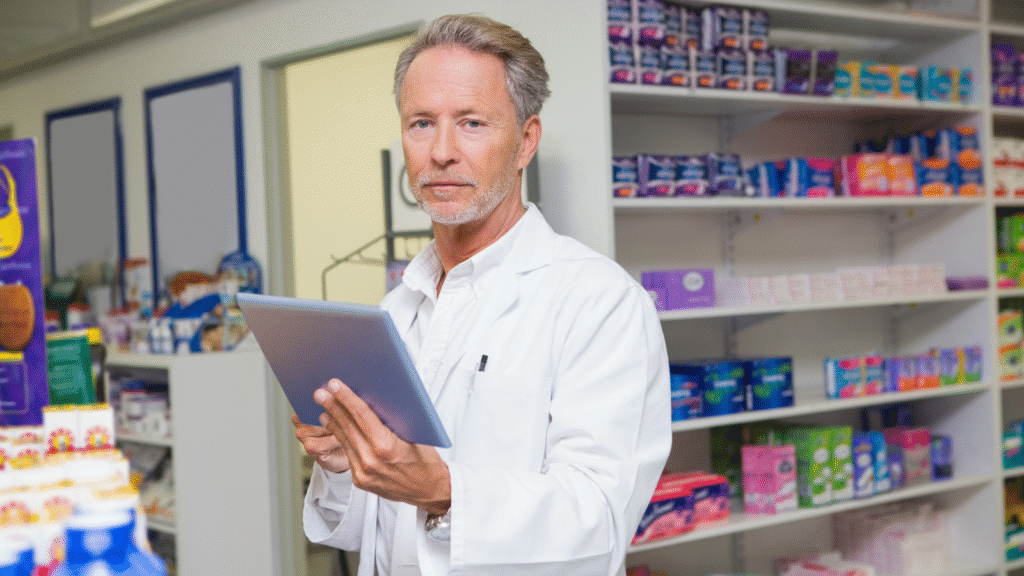
サルコペニア対策における薬剤師の役割は、次の3点に集約されます。
- 服薬内容の適正化(ポリファーマシーの是正)
- サプリ・漢方などの相談対応と提案
- PTや管理栄養士との情報連携による安全な支援体制の構築
運動や評価は専門職に任せ、薬剤師は安全・栄養・薬学的視点からチーム医療に貢献することが現場で求められる姿です。
「もっと高齢者医療に携わりたい」「在宅医療の中で専門性を高めたい」と感じたら、老年医療に強い職場で経験を積むのもひとつの選択肢です。転職エージェントを活用して、自分の専門性を活かせる環境を探してみてはいかがでしょうか。
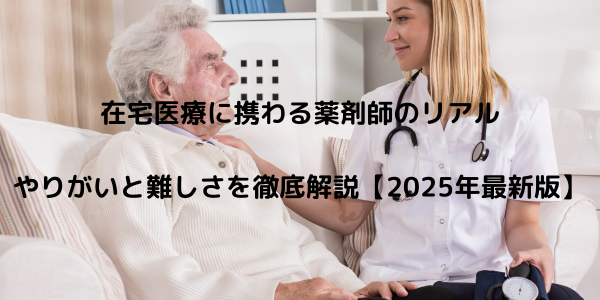

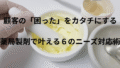
コメント