感覚過敏とは、音や光、匂いなどの刺激に対して過剰に敏感になる状態のことです。特にHSP(Highly Sensitive Person=非常に敏感な人)の特性を持つ人は、こうした刺激を人一倍強く感じやすく、日常生活や仕事の場面で大きな負担を感じることがあります。
薬剤師の職場は、調剤機器の音、強い照明、薬品や消毒液の匂いなど、刺激が多い環境です。「なんだか疲れやすい」「職場にいると頭痛や不快感が増す」という人は、実は感覚過敏やHSPの影響を受けているのかもしれません。
感覚過敏やHSPは我慢してはいけない問題

感覚過敏やHSPの人の中には、「職場で迷惑をかけたくない」「自分さえ我慢すればいい」と思い込んでしまう方が少なくありません。しかし、無理を続ければ、ストレスや疲労がたまり、頭痛、めまい、集中力低下、メンタル不調へとつながる危険があります。こうした状態は、個人の健康だけでなく、調剤ミスなどのリスクを高める職場全体の問題でもあります。だからこそ、本人だけでなく職場全体で「刺激を減らす工夫」を考えることが大切です。
また、HSPや感覚過敏は決して「心の弱さ」ではなく、生まれつきの気質や体質によるものです。必要に応じて、心療内科や精神科、産業医など医療の専門家に相談し、適切なアドバイスや支援を受けることも検討してください。
すぐできる!薬局での具体的な刺激対策

感覚過敏やHSPによる負担は、ちょっとした工夫でぐっと軽減することがあります。ここでは、薬局で実践しやすい具体策を紹介します。
- 音の刺激を減らすには
調剤機器のアラーム音やピッキング音は設定で音量を下げられる場合があります。必要以上に大きな音になっていないか確認しましょう。休憩中は、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを使って耳を休めるのも効果的です。なるべく静かなスペースで行える作業(在庫整理、伝票作業など)を調整するのも一案です。 - 光の刺激を減らすには
ディスプレイの明るさやコントラストを調整したり、ブルーライトカットメガネを使うのもおすすめです。作業の合間に目を休める時間を意識的に取ることも重要です。 - 匂いの刺激を減らすには
調剤室や待合室の換気を徹底し、薬品や消毒液の匂いがこもらないようにします。必要以上の消毒液使用を避けたり、香料の強い柔軟剤・香水の職場使用を控えることも有効です。苦手な臭いを特定し、それを避ける行動をとることも大事です。
自分に合う働き方を少しずつ見つけよう

感覚過敏やHSPは個人差が大きく、「これをすれば全員が楽になる」という万能な解決策はありません。だからこそ、自分が一番つらいと感じる刺激を特定し、できるところから改善を試みるのが第一歩です。
一人で抱え込まず、信頼できる職場の仲間や上司に相談し、理解を得ることで協力を得やすくなります。また、心身の状態が深刻な場合は、早めに医療機関に相談し、必要に応じて休養や治療を検討することも重要です。
それでも職場での改善が難しい場合、感覚過敏やHSPに配慮した働き方を探すのも一つの選択肢です。最近では、在宅勤務ができる医療系企業や、調剤現場以外の職種(医薬品情報提供、治験関連業務など)で活躍する薬剤師も増えています。
自分に合った職場で、もっと快適に働くために

感覚過敏の悩みを抱えながら毎日仕事を続けるのは、思っている以上に心身の負担が大きいものです。「音や光、匂いがつらくて集中できない」「周囲に理解されないのがつらい」そんな悩みを一人で抱え込んでいませんか?
無理を続けることで体調を崩してしまったり、「もう薬剤師を続けられないかもしれない」と悩んでしまう人もいます。しかし、実際には感覚過敏に理解のある職場や、配慮の行き届いた職場環境は確実に存在します。最近では、在宅勤務ができる医療系企業や、調剤現場以外の仕事(医薬品情報提供・治験関連業務など)で活躍する薬剤師も増えています。
もし今の職場で改善が難しいと感じたら、無理をせず、新しい環境を探してみるのも一つの選択肢です。転職エージェントに相談すれば、あなたの希望や条件に合う求人を一緒に探してくれるだけでなく、感覚過敏などの悩みを事前に職場に伝えやすくなるサポートも受けられます。
今の悩みを解決し、あなたらしく働ける場所を見つけるために、一度プロに相談してみませんか?
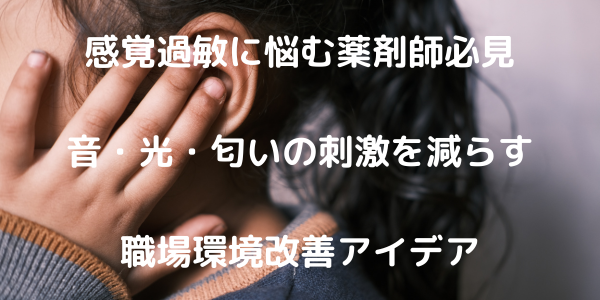
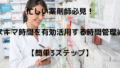
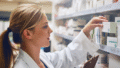
コメント