精神疾患を発症したときは、まず「治療に専念すること」が最優先です

薬剤師という責任の重い仕事の中で、精神的に限界を感じる瞬間は誰にでも起こり得ます。うつ病、不安障害、適応障害などを発症し、「この先、自分は薬剤師として働けるのか」と不安になる方も多いでしょう。
ですが、今最も大切なのは、無理に働き続けることではなく「治療に専念すること」です。あなたの価値は「働けているかどうか」ではなく、「生きていることそのもの」にあります。
まずは焦らず、心と身体を休めることに集中しましょう。
治療を優先すべき理由と、薬剤師としての未来を諦める必要がない理由

精神疾患は、頑張りすぎた人が陥りやすい病気です。決して「弱いから」ではありません。ですが、働きながら治療を続けるのは難しく、回復に時間がかかることも少なくありません。
休職が可能な場合は、主治医の診断書を提出し、傷病手当金を申請することで、最長1年6ヶ月の間、給与の約2/3が支給されます。これにより、収入面の不安を減らしながら治療に専念できます。
また、たとえ退職したとしても、薬剤師という国家資格が消えることはありません。体調が整ってから、パートや企業薬剤師、在宅医療、事務系職種など、無理のない働き方に切り替えることも可能です。
薬剤師のキャリアは一つではありません。「今は休む時期」と受け入れることが、未来のあなたを守る一歩になります。
実際に取り入れられる工夫と働き方

精神疾患を抱えた薬剤師でも、自分のペースを大切にしながら働く方法はさまざまにあります。ここでは、実際のケースではありませんが、現実的に取り入れられる工夫や働き方の選択肢をご紹介します。
- 休職と傷病手当金を活用して、一定期間は治療に専念する
無理に働き続けるよりも、まずは心身の回復を最優先することが大切です。 - 退職後、就労移行支援や職業訓練を活用して、無理のないペースで社会復帰を目指す
医療現場以外での働き方(事務職、企業薬剤師など)を検討することもできます。 - 復職が難しい場合は、障害者雇用枠での就職を検討する
勤務時間や仕事内容に配慮された環境で、自分らしく働く道もあります。 - パートや時短勤務から少しずつリスタートする
週1〜2日から勤務を再開し、体調に合わせて働く時間を調整していく方法も有効です。
これらはあくまで「可能な選択肢の一例」ですが、重要なのは、薬剤師としての働き方に一つの正解はないということです。あなたに合ったスタイルを見つけていくことが、長く続けるコツになります。
働くことより、まずは「治すこと」が大切

精神疾患を抱えたとき、多くの人が「いつ職場に戻れるだろう」「ブランクが不利にならないか」と不安になります。
しかし、無理をして働き続けることは、回復を遅らせるどころか、症状を悪化させてしまう原因にもなります。
精神疾患の回復には、「時間」と「安心できる環境」が不可欠です。
脳や心が疲弊している状態では、通常の判断や集中すら難しくなることがあり、まずは心身をしっかりと休ませることが、長い目で見て最も効率的な選択です。
「復職しなければ」「転職活動をしなければ」と焦る必要はまったくありません。
社会や仕事はいつでもあなたを待っていますが、あなたの心と身体は、あなた自身が守らなければなりません。
体調が回復すれば、再び働ける場所は必ず見つかります。焦らず、まずは「治療に専念する」と心に決めて、自分自身を大切にしてください。
制度を活用し、ゆっくり次のステップへ

精神疾患を抱えたとき、無理に前に進もうとすることが、かえって回復の妨げになることもあります。
そんなときは、「立ち止まる」ことを選んでいいのです。
今のあなたに必要なのは、「頑張る」ことではなく、「自分を守る」こと。
そのために使える制度や支援を、知らないままにしないでください。以下は、精神的にしんどいときでも使える制度や相談窓口です。
傷病手当金:働けない間の生活を支える収入補償制度
会社員や公務員など、健康保険(社会保険)に加入している人は、病気やケガで働けなくなったとき、最長1年6ヶ月間、給与の約2/3が支給される制度があります。
医師の診断書が必要ですが、「働けないこと」に対して経済的な不安を軽減してくれる大切な制度です。
休職制度:診断書を提出すれば一定期間、職場を離れて治療に専念できる
就業規則に休職の制度がある場合、医師の診断書を提出すれば、一定期間会社を休んで治療に集中することが可能です。
休職中も傷病手当金を受け取れることが多く、安心して療養に専念できます。復職については医師の意見や職場との相談により決まるので、無理せず段階的な復帰も可能です。
退職後の傷病手当金継続受給:退職しても手当が止まらない場合がある
もし休職中に退職を選んだとしても、条件を満たせば傷病手当金をそのまま継続して受け取ることができます。
退職日の時点ですでに手当を受給しており、引き続き治療が必要とされている場合が対象です。社会保険の任意継続手続きを行うことで、その後も受給が可能になります。
精神保健福祉センター・ハローワーク・就労移行支援:頼れる公的な相談窓口
精神疾患に関する悩みは、専門機関に相談することで、解決の糸口が見つかることがあります。
- 精神保健福祉センター:心の病に関する相談窓口。医療や福祉サービスの紹介もしてくれます。
- ハローワーク:精神疾患を抱える方向けの就職相談・職業訓練の案内あり
- 就労移行支援事業所:治療が落ち着いたあとに、仕事へ復帰するためのスキル訓練や職場体験ができる福祉サービス
キャリアに迷ったら、薬剤師専門の転職エージェントに相談するのもひとつの手段

治療を終え、働く意欲が戻ってきたとき、「どんな職場が自分に合うのかわからない…」という悩みにぶつかることもあるでしょう。
そんなときは、薬剤師専門の転職エージェントに相談するのもおすすめです。体調や働き方に配慮した求人の提案や、職場選びのアドバイスを受けることで、無理のないキャリア再構築が可能になります。
焦らず、ひとつずつ進んでいきましょう。
あなたのペースで大丈夫です。
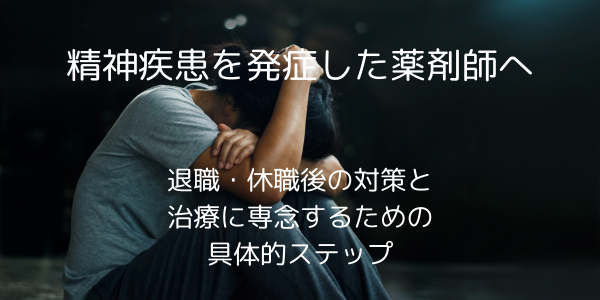


コメント