医療現場では「チーム医療」が求められるようになり、薬剤師も多職種と連携しながら患者さんのケアに関わる場面が増えています。
しかし実際には、「意見が通らない」「自分の役割が伝わらない」といった悩みを抱える薬剤師も少なくありません。
本記事では、薬剤師が多職種連携の中で直面しやすい課題と、その壁を乗り越えるための具体的な工夫をご紹介します。
特に現場で孤独感を感じている方や、「自分の専門性が活かせていない」と感じている方のヒントになるはずです。
なぜ薬剤師は多職種連携で悩むのか?

薬剤師が医師や看護師、栄養士、リハビリ職などと連携する「チーム医療」の重要性は年々高まっています。しかし現場では、連携がうまくいかずに悩む薬剤師が多いのが実情です。その理由として、以下のようなケースがよく見られます。
- 発言しにくい雰囲気
医師や看護師が中心となるカンファレンス(患者について話し合う場)では、薬剤師が口を挟むタイミングをつかめず、黙ってしまうことがあります。「話を遮ってしまうのでは」「場違いかもしれない」という遠慮から、意見が言えなくなってしまうのです。
- 薬剤師の役割が理解されていない
「薬を渡す人」「処方通りに調剤するだけ」というイメージを持たれがちで、医師や看護師に対して薬剤師の専門性が十分に伝わっていないことがあります。そのため、副作用のリスクや用法・用量の見直しなどの重要な指摘が、軽視されるケースもあります。
- 医師・看護師との価値観のズレ
薬剤師が患者の副作用や生活状況に配慮して提案をしても、医師側が「今のままで問題ない」と判断し、薬の変更や中止を却下されてしまうことがあります。医療職間での“判断基準の違い”が、円滑な連携の妨げとなるのです。
- 情報共有が不十分
「処方意図が口頭のみで伝えられる」「カルテにアクセスできず、患者情報を十分に把握できない」など、他職種との情報格差があると、連携しにくくなります。薬剤師としての介入が遅れたり、適切な提案ができなかったりすることもあります。
このように、物理的な距離だけでなく、認識の違いや関係性の問題が、薬剤師の孤立感を生む原因になっているのです。
放置すると、どうなるのか?

これらの悩みをそのままにしておくと、薬剤師としての専門性が十分に発揮できず、さまざまな悪影響が出てきます。
- 孤立感が強まる
周囲と会話が少ないまま日々の業務をこなすことで、「チームの一員」という実感が持てなくなってしまいます。やがて「いてもいなくても変わらない」と感じてしまう危険も。
- 患者への介入機会が減る
薬剤師は本来、薬の選択や副作用の回避、服薬状況の調整などで患者を支える存在です。しかし意見を言えない状況では、薬学的なサポートが行えず、結果的に患者に不利益が生じてしまうこともあります。
- スキルが発揮できない
大学や実務で学んできた知識や経験が、現場で活かされないまま時間だけが過ぎてしまいます。薬剤師としての成長や手応えが感じられず、やる気の低下にもつながります。
- 自信を失う
何度提案しても却下されたり、話を聞いてもらえない経験が重なると、「自分の意見には価値がないのかも」と感じてしまいます。結果的に自己肯定感を失い、転職や離職を考えるきっかけにもなります。
連携の悩みは、見過ごしてはいけない「専門職としての根本的な壁」です。だからこそ、解決の糸口を見つけることが重要です。
多職種と連携を深めるための工夫

では、薬剤師がチーム医療の中で存在感を発揮し、信頼を得るにはどうすればよいのでしょうか?
いくつかの具体的な工夫をご紹介します。
● コミュニケーションを変える工夫
相手の立場を尊重しながら、患者の情報をベースに提案を行うことで、意見の通りやすさが大きく変わります。
実例1
「患者さんの認知機能の状況から、1日3回の服用は難しそうです。1日1回で済む薬に変更は可能でしょうか?」
→ 医師も「なるほど」と思える根拠があると、意見が通りやすくなります。
実例2
「現在服用中のベンゾジアゼピン系薬剤で、日中のふらつきや物忘れが目立っています。ベルソムラなどへの変更で、生活の質が改善できるかもしれません。」
→ 薬剤師ならではの視点で、副作用を減らしつつ治療効果を維持する提案ができます。
ワンポイント
- 感情的にならず、結論→理由→提案の順で話すと、スムーズに伝わります。
- 相手を「否定する」ように聞こえない工夫も大切です。
● 存在感を高めるための工夫
- カンファレンスや回診に積極的に参加し、「薬剤師がいると助かる」と感じてもらう
- 薬学的介入内容をメモやレポートで共有することで、チーム内での影響力を広げる
- 患者の変化を報告する(例:「減薬後、倦怠感が改善されたようです」)
自分の仕事が患者の改善につながっていることを他職種に示すことが、信頼の第一歩になります。
● スキルを磨くための工夫
- 他職種向けの勉強会や説明会で講師を務める
- 臨床薬学やコミュニケーションスキルの研修に参加し、提案力を強化する
薬剤師としての「専門性」+「対話力」があれば、どんな職場でも求められる存在になれます。
今の職場では難しい?それなら働き方を見直すタイミングかも

これまでご紹介した工夫を試しても、「やはり意見が通らない」「風通しが悪い」と感じるなら、環境そのものを見直す必要があるかもしれません。
例えば…
- チーム医療が根付いている在宅医療の現場
- カンファレンスでの薬剤師の発言が制度的に保障されている病院
- 連携の評価が人事評価に組み込まれている法人
などでは、薬剤師の専門性が活きる場面が格段に多くなります。
多職種連携で活躍できる薬剤師になるための次の一歩

まずは、今の職場で「ちょっとした提案」や「一言の工夫」から始めてみましょう。
それでも状況が変わらなければ、「もっと発言しやすい環境」を探すことも大切な選択肢です。
薬剤師専門の転職支援で、自分らしく働ける環境を見つけよう

多職種連携に悩む薬剤師は少なくありません。
だからこそ、「薬剤師の専門性が評価される職場」への転職を考えることは、決して逃げではありません。
薬剤師専門の転職エージェントなら、あなたの希望や得意分野に応じて、
「発言しやすい」「連携しやすい」職場を一緒に探してくれます。
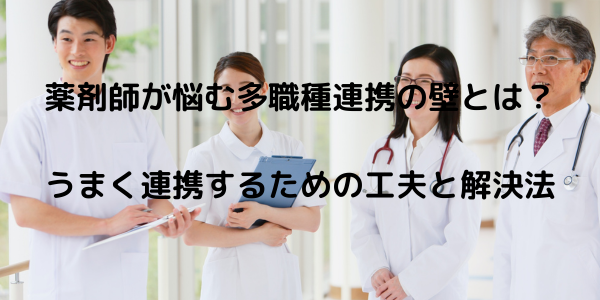
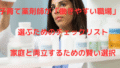
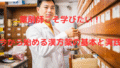
コメント